ブランクがあるため、薬剤師の復帰に不安を感じ、迷ってはいませんか?
復帰したいと少しでも思っているようであれば、躊躇しているのは勿体ないと思います。
ブランクの長さによって、やっておくべきことは違ってきます。
- ブランクがある薬剤師で復帰を考えている人
- 復帰に迷っている人
- 復帰前の薬剤師で勉強したい人
どのくらい薬剤師のブランクがあいていますか?

ブランクとひとくくりにいっても人それぞれ長さがちがいます。
私自身は3年程度実務経験を得て6年休職していたため、かなりのブランクがある部類に入ります。
不足している自覚をもって準備していてよかったと思いました。
薬剤師を取り巻く環境はここ10年の間に大きく変わりました。
薬剤師の転職市場に関するエージェントの見解はこちら↓

10年以上前の売り手市場だった頃のイメージで、知識も実力もないのに上から目線で入社すると、仕事についていけず、1ヶ月以内に辞めることになってしまいます。
 かばこ
かばこわたしのあとに入った薬剤師は2人ほど知識不足でやめていきました。
卒業後一度も働いていない!もしくは5年以上のブランクがある薬剤師向け


5年以上のブランクが開いている場合は新卒の薬剤師と同じレベルか、それ以下まで落ちている覚悟で勉強したほうがよいでしょう。
本当にそれくらい薬の知識が抜け落ちています。
5年の間に大きく変わった薬剤師の仕事内容
10年ほど前までは、薬剤師は薬を管理し、医師の処方通りに調剤していれば加算が取れていました。
あまり知識がなくとも仕事を続けられていた薬剤師がたくさんいました。
しかしここ数年、調剤報酬改定の方向は「対物から対人へ」とシフトし、それに伴い薬剤師の仕事内容もおおきく変わってきています。
またコンピューター化がすすみ、電子薬歴、電子カルテはもちろんのこと、添付文書が紙で確認できない時代になりつつあります。
マイナンバーカードが医療情報と紐づいたことにより、さらにその動きは加速しています。
具体的に変わった薬剤師の仕事内容とは?
具体的に6年ぶりに復帰して驚いたことを以下にまとめました。
電子薬歴が基本
ある程度コンピューターが扱えることは基本となっています。
添付文書を深くチェックは常識
昔は添付文書が紙だったため、細かい確認はおこなっていませんでした。
今は詳細まで確認しています。
処方箋に検査値が掲載されている
病院によってシステムが異なりますが、大きな病院では検査値が掲載されています。
またそれを活用することも求められています。
トレーシングレポートが始まった
医師に対して、情報提供を行うシステムです。
疑義紹介を行うほどではないけれど、治療上必要と判断したことを医師に報告するお手紙のようなものです。
吸入指導加算が始まった
喘息の吸入の指導をしっかりと行い、それを病院に報告書を提出することで算定出来ます。
吸入の手技ができておらず結果の出ない患者さんが多いため、現在は医師の方から吸入指導をおこなうように指示がでる場合もあります。
特定薬剤管理指導加算2がとれるようになった
抗がん剤を院内で投与している人が、薬局でも抗がん剤や副作用に関する薬が出ている場合、その患者さんに対して、次回受診日までに電話等でフォローを行い、病院に結果報告を行った場合に算定出来ます。
お薬手帳の確認と相互作用の確認は必須になった
以前はお薬手帳を持ってこない患者さんも多く、確認をとれないこともありました。
しかし今はお薬手帳の持参が常識のため、お薬手帳の確認が漏れていると、薬剤師としての資質や場合によっては責任が問われます。
かかりつけ薬剤師制度がはじまった
上記の内容とも重複しますが、かかりつけで担当している患者さんのすべての薬をフォローする必要があります。
ジェネリック医薬品が増えた
先発品の名前しか知らないと、何が何だか分からなくなります。
トレーシングレポートって何?という方はこちら↓


ブランクが長いと薬剤師の復帰はむずかしい?昔よりも大変だけど、頑張れば可能!
上記の変更内容だけをみると、無理なのではないかと不安になってしまうかもしれません。
しかし復帰してすべてを一度にできるようになる必要はありません。
ただし、薬の知識の蓄えは急には増えません。
ある程度は書籍等から補ってから復帰しないと周りからも患者さんからもよく思われません。
場合によってはクレームにも繋がりかねません。
自信がなければいきなり総合科目の病院前は避けよう!
最近はかかりつけ薬局制度や、お薬手帳持参により、幅広い知識をどの薬局でも求められる傾向にはありますが、やはり総合病院前よりは遥かに少ないでしょう。
経験や知識が浅いまま歳をとると、だんだん就職先が狭まってくる
前述したように、復帰直後で自信がない場合は整形外科の門前やクリニックの門前で慣れていったほうがよいでしょう。
チャレンジできるようであれば、少しでも若いうちに勉強できる職場に身を置いた方がよいと思います。
ブランクが長い場合は、どこから勉強したらいい?
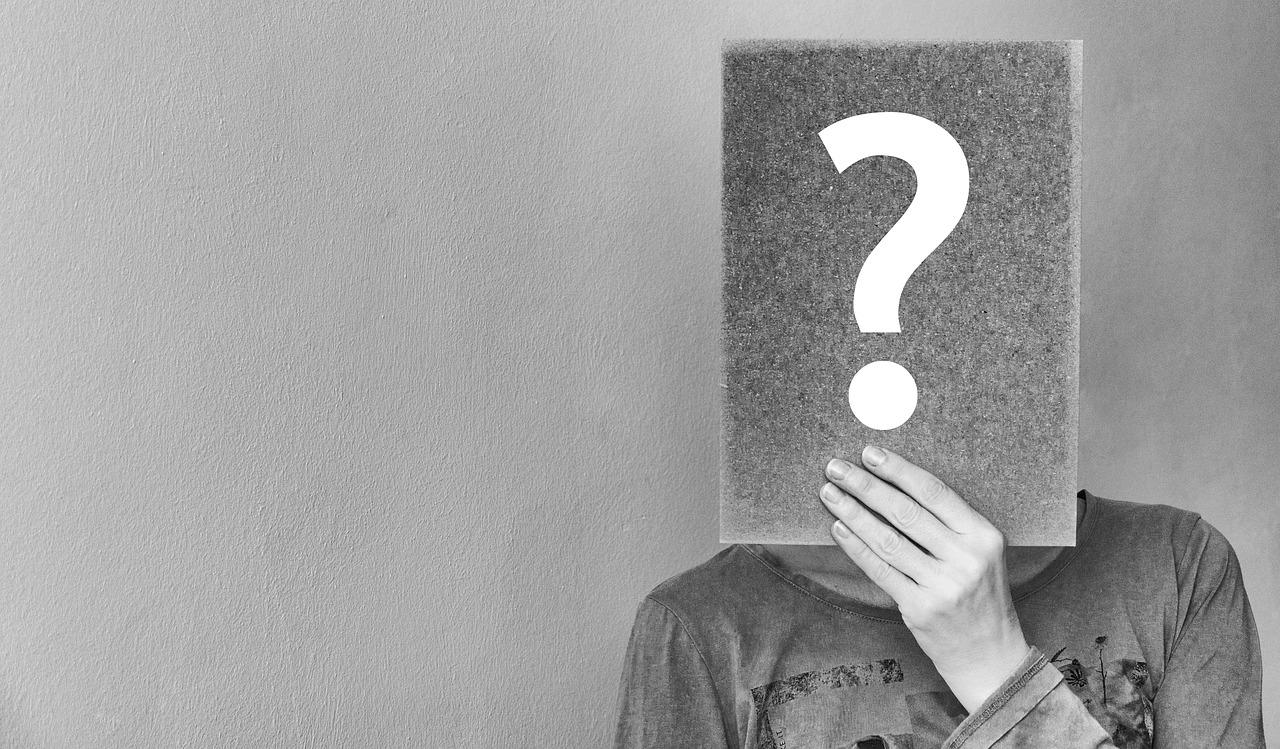
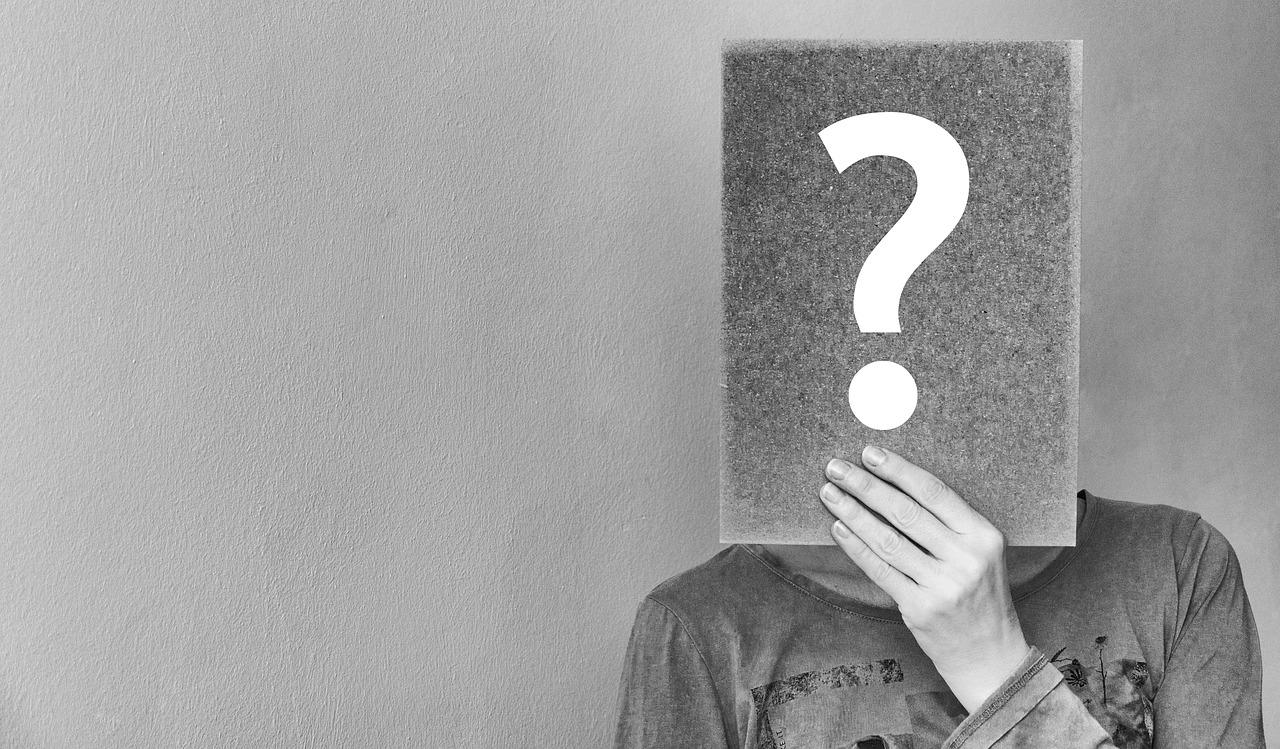
え、そんなに?と思うくらい基礎から始めた方がいいと思います。
長いブランクの間に基礎までガタガタになっているため、学生時代に戻るくらいのつもりでやったほうがよいでしょう。



私自身が薬の知識をすっかり忘れていました!
勉強するのにおすすめの書籍情報はこちら↓私自身が実際に使用してよかった書籍をまとめています。
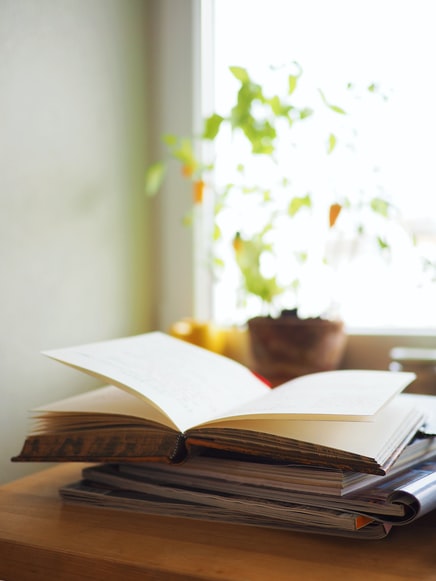
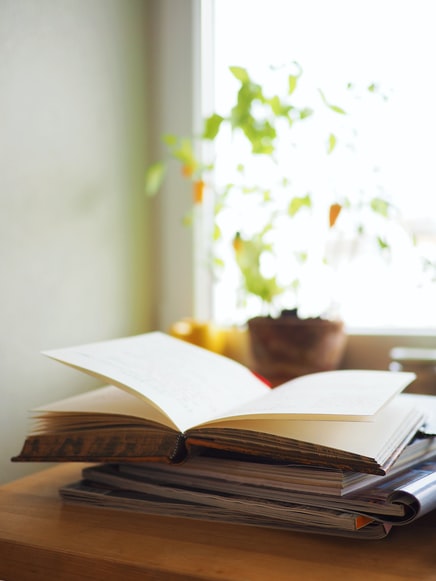
復帰のいつぐらい前から勉強するのがおすすめ?
そのくらいはこのブランクの長さを考えると勉強に費やしたほうがよいと思います。
3年以上5年未満のブランクのある薬剤師向け


休職5年以内、休職前に5年以上職歴があるなどの場合は意外に色々覚えているため、基礎は飛ばしてもよいと思います。
その辺を中心に補ったほうがよいでしょう。
勉強するのにおすすめの書籍情報はこちら↓私自身が実際に使用してよかった書籍をまとめています。
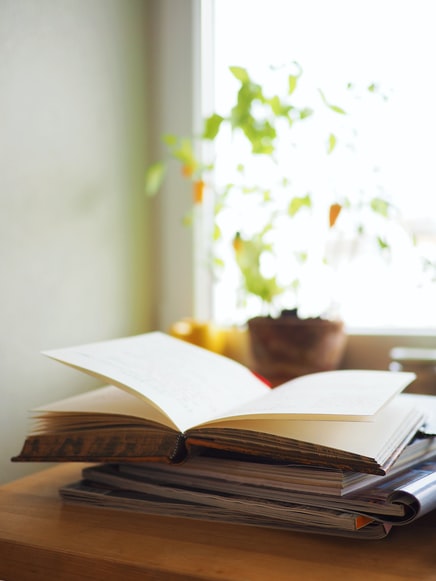
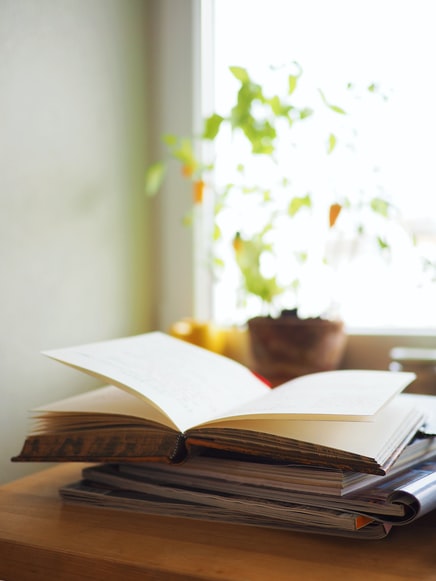
ブランクは1年以内(産休、育休中など)の薬剤師向け


仕事をしているときには忙しくてゆっくり勉強する暇もなかったかと思うので、この休職中に勉強してパワーアップしてはいかがでしょうか?
おすすめの書籍情報はこちら↓
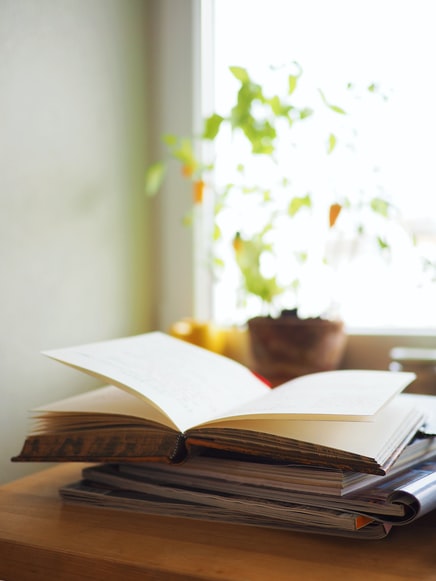
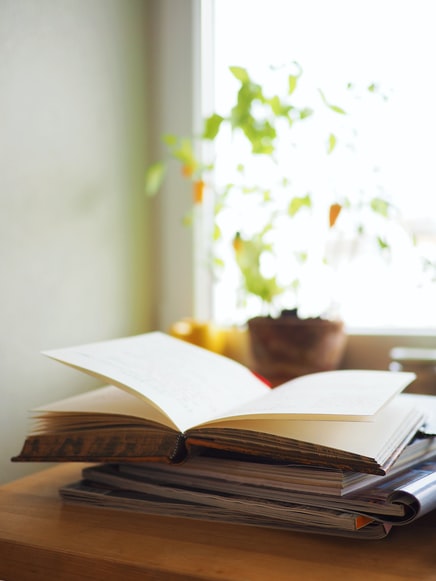
転職活動や復帰後の人間関係に不安がある場合はどうすればいい?


どのブランクの方でも、不安が一切ないという人はいないと思います。
ほとんどの薬剤師が利用しています。
紹介会社を使うと、営業がうるさいのがデメリットですが、利用料はかかりません。
私自身の転職体験はこちら↓




圧倒的な求人数!セルワーク薬剤師に関する記事はこちら↓


就職先に早く慣れる為の工夫に関する記事はこちら↓


おわりに


この記事では、復帰に不安になっている薬剤師向けに、復帰後の変化と準備したほうがよいことをまとめました。
闇雲に不安になっても仕方がありません。
もしも少しでも復帰したいという気持ちがあるようであれば、ぜひ諦めないでください!
