復帰に向けて勉強したいけれど、どの書籍で勉強したらよいか悩んでいませんか?
薬剤師の専門書って高いし、ある程度大きな本屋に行かないと実物が見れないから買うのが怖い…。
大きな本屋でも欲しい専門書が置いていなくてがっかり…。
ネットはレビューが少なすぎて買うかどうするか迷う…という人のために、私自身が勉強に使用した書籍を紹介しました。
ブランクの長さに応じて、ぜひ勉強法の一つとして組み込んでみてください。
どうしてこの分類になっているの?と思う人は前回の記事を参考にしてください。↓

書籍のおすすめ度は5段階評価で★~★★★★★で表現しています。
- ブランクがある薬剤師で勉強したい人
- 薬剤師に転職予定の人で勉強したい人
- 復帰前の薬剤師で勉強したい人
卒業後一度も働いていない!もしくは5年以上のブランクがある薬剤師向け

このタイプの人は、明らかに知識と基礎力が不足しています。
ソースは私自身です。
わたしは3年の調剤経験、6年のブランクから復帰しましたが、勉強せずに復職したら恐ろしいことになっていたと確信しています。
基礎を勉強することから始めたほうが良いと思います。
基礎編
基礎の薬理だけれど、商品名も一緒に覚えられ、実際の現場に出ても知識として使えるものを紹介しました!
薬が見えるシリーズ
おすすめ度 ★★★★★
vol 1~vol4まであり、一冊3600円程度と非常に高額なのですが、読む価値があると思います。
カラフルでかわいく、非常にわかりやすくまとめてあり、最新のものを買えば新薬も掲載されています。
今は学生も、このシリーズを国家試験対策に使っているようです。
必要十分な医療知識、成分名、商品名のどちらも記載があるため、じっくり読みこめば、かなり力がつくことは間違いないです。
ここに掲載されているすべてを覚えるというよりは、大学時代、仕事をしていた知識を思い出しながら、知識を整理してアップデートするのに使ってください。
抗がん剤のところは、薬局薬剤師では、この書籍のみでは頭に残らないため、とりあえずそこは読み飛ばしてよいと思います。
薬局では、抗がん剤の深い知識を必要とされる機会は少ないため、勤めながら不足を補っていく形でも、十分間に合うと思います。
 かばこ
かばこブランク復帰直後の薬剤師に、いきなり抗がん剤の監査をさせる薬局もないと思います。
一番頻出する成人病関係(高血圧、高脂血症、糖尿病)の薬と腎臓のところは、必ずよく読み込んでください。
ここの知識がないと、ついていけず、恥ずかしい思いをするかもしれません。
単科目薬局から総合科目薬局に転職の際の勉強や、参考書代わりとしても家にあってもいいと思えるような本です。
病気が見える
おすすめ度 ★★
病態の情報が欲しい場合は、こちらの書籍を手に取ってもいいですが、内容としては薬剤師が学ぶにしては難しいという印象を受けました。
お金に余裕があれば、辞書代わりとして自宅にあってもいいと思います。
研修医レベルの知識は網羅されていそうだと感じました。(実際研修医がどのくらいの知識があるのかは正確にはわかりませんが…)
薬の比較と使い分け
おすすめ度 ★★★★★
この本は6割から8割は頭に入れるつもりで読み込んでください。
仕事に復帰してある程度知識がつくと、書いてあることのほとんどが基礎であることに気がつきます。



復帰前に最初に読んだ本です。
参考にしている資料、論文等もきちんと記載があるため安心できます。
演習編
勉強したことをアウトプットしなければ、なかなか知識は身に付きません。
現場にでている薬剤師でも勉強になる深い知識も多く含まれています。
日経DIクイズシリーズ
おすすめ度 ★★★★★
いわずと知れた日経DIのクイズコーナーをまとめた本です。
薬局薬剤師でこの本を知らない人はいないでしょう。
毎月届くDIクイズをふむふむと読んでいた人も多いはず。
ただ、休職中は高額のため、読めていなかった人も多いと思います。
私はまとめたものを3冊買ったのですが、どのクイズも被っておらず、大変勉強になりました。
日経DIのクイズは結構難しいため、ほとんど正解にたどり着けないのですが(今でもそうですし、ほかの方もそういってます)、解説がとても分かりやすく、この本で習ったことのお陰で現場で対応できたこともあります。
時間があれば3冊全て解いてみてください。
3年以上5年未満のブランクの薬剤師向け


忘れてしまっていても、何かのきっかけがあれば思い出せるレベルの知識があるのがこの層の方々だと思います。
先ほどもっとブランクの長い方におすすめした 、薬の比較と使い分け と 日経DIクイズシリーズ も同じように得るものはあると思うのですが、あえてもう少し応用編を紹介します。
応用編
基礎編ではもの足りない!
極める小児の服薬指導
おすすめ度 ★★★
子供をお持ちの方であれば、ぜひこの経験を薬剤師の仕事に活かしたいと思いますよね。
ただ、サンプルはわが子のみでは心許ないものです。
子供と言っても人それぞれ個性や病気が異なるからです。
著者は小児薬物療法認定薬剤師の資格も取得しており、少し専門的すぎる情報が多いようにも感じましたが、十分に現場で活かせる知識がつきます。
高齢者の安全な薬物療法ガイドライン
おすすめ度 ★★★★
薬局に来る患者さんのほとんどは高齢者だと思います。
高齢者は多剤服用傾向にあり、よく薬を確認しないと薬害を起こす危険性が高い患者さんです。
認知機能低下、転倒リスク上昇、腎機能低下に注意が必要な薬を中心に、高齢者に注意が必要な薬が、推奨度、理由と共にまとまってリストアップされています。
添付文書で禁忌かどうかという1つの指標だけでなく、禁忌でなくても、高齢者にリスクが高い薬が出ている場合には、投薬時にもよく注意して症状を聞き出すことが重要だと思います。
気がついた場合には早めに医師に報告することも大切です。
検査値×処方箋の読み方
おすすめ度 ★★★
総合病院の門前薬局では、処方箋に検査値が掲載されることが増えています。
マイナンバーカードによって、今後よりその傾向は高まってくると思います。
私たちは薬の専門家なので、医師にない視点で検査値を活用していかなければならないと思います。
医師は検査値は基本的に病気の進行や改善度合いを見るために使用しており、薬の副作用という観点ではあまり細かくは見ていません。
その点に注意して検査値を確認し、気がついた時には早めに医師に報告すると、よりよい医療の提供に繋がっていくのではないでしょうか。
薬物動態を推理する55クエスチョン
おすすめ度 ★★
そもそもTDMを使わないといけないような注射薬は院外に出ませんし、のんびりと計算している暇もありません。
またわかったところでどう活かせばいいのかもよくわからないものです。
ただ、定常状態になる薬とならない薬の違い、薬はいつごろ効いてきて、いつごろ効果が切れてくるのかということは理論上でもわかっておいたほうがいいと思います(臨床上の感じ方はそれぞれなので、必ずしも理論上の数字通り薬が効いてくるとも限りませんが…)
医師の中には定常状態になる薬にもかかわらず、やたらと分1の薬を分2で出してくる先生がいて、コンプライアンス低下に繋がる例もあります。
ブランクは1年以内(産休、育休中など)の薬剤師向け


ブランクがあるといっても1年程度であれば、ほとんどの事は覚えている状態での復帰だと思います。
仕事をしているときには忙しくてゆっくり勉強する暇もなかったかと思うので、この休職中に勉強してパワーアップして復帰できる本を紹介します。
薬局で使える実践薬学
おすすめ度 ★★★★
かなり難しめです。
ベテランの薬剤師に「貸してほしい」と言われて貸しましたが、「無理だ」と言って返却されてきました。
かなり分厚く、参考書のような厚みがあり、ひるんでしまうような文章量です。
どちらかというと日経DIクイズをさらに深掘りした書籍です。
ここで教えてもらったK値低下で致死性不整脈上昇のリスクが上がるという知識は大変役に立ち、先日他院でカリメート服用中でK値が下がりすぎた患者さんの薬を止めることができました。
この時にただK値が下がっているから…ではなく、心疾患を持っているのでK値低下は危険だと伝えたところ、医師がすぐに患者宅に電話して止めてくれました。
異常値の読み方が身につく本
おすすめ度 ★★★
私の薬局では尿検査結果の記載もあります。
しかしその読み方がさっぱりわかりませんでした。
これを読んで少しわかるようになりました。
パニック値をご存知でしょうか?
どの施設にも基準があり微妙に異なるのですが、この数値を上回ったり下がったりした場合は、非常に危険性が高いといわれている臨床検査の数値の事で、再検査や入院対象になる数値です。
頻繁にはこの数値にかかった患者さんを薬局で見かけることはありません。
しかし働いていて数例危ない患者さんに遭遇し、疑義紹介やメーカーへの問い合わせに使わせていただいたことがあります。
検査値からさまざまな病態を類推もできるようになるため、お勧めの一冊です。
ただ、これも難しめの為、完全な理解はできないと思います。
番外編(もっていると便利な書籍など)
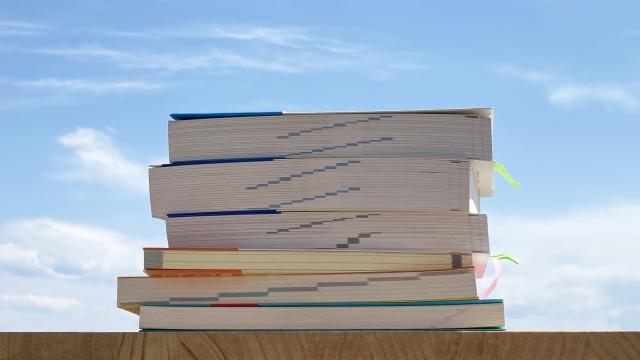
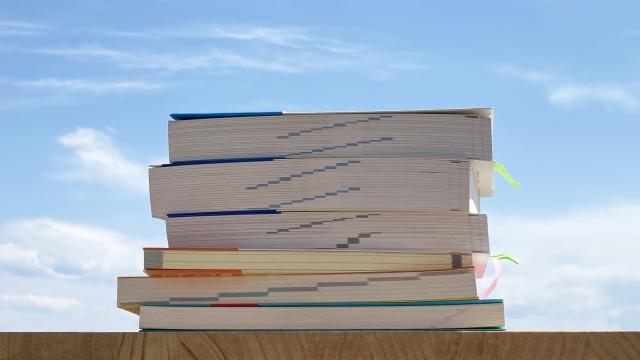
スキルアップではないですが、手元のあると便利な書籍や、モチベーションアップに役立つ書籍を紹介します!
薬剤師としてのモチベーションアップのための本
ブランクがあると、復帰するのにエネルギーが必要です。
薬剤師3.0
おすすめ度 ★★★★
日本在宅薬学会 理事長でファルメディコ株式会社の社長兼医師の狭間研至先生が書かれている本です。
薬剤師に対して「対物ではなく対人」「医師のように問題を解決する姿勢を」と書籍の中で説いています。
薬剤師の将来の事をよく考えていて熱い思いがあふれています。
少し医師なので「?」と思う発言もなくはないですが、「薬学の知識をもって問題を解いていってほしい」という熱い思いには心を打たれるものがありました。
いまでも、ときどきこの本のセリフが頭によみがえります。
薬局になければ自分用に揃えておきたい書籍
仕事をしていてわからないことをすぐに調べられる便利な辞書的な書籍です。
新小児用量改訂版
おすすめ度 ★★★
小児用量を調べるときに役立ちます。
腎機能別薬剤投与量POCKET BOOK
おすすめ度 ★★★★★
これも薬局に本来はあるべきだと思うのですが、置いてないところも多いようです。



この書籍のデータを医師にそのまま見せても問題ありません。
OTC医薬品の知識と使い分け
おすすめ度 ★★
前述した薬の比較と使い分けのシリーズです。
ドラッグストアの経験はないけど、まったく知らないのは薬剤師として恥ずかしい、投薬時にOTCの事を聞かれても答えられないなどの対策として購入しました。
この分野の薬はドラッグストアでも同じような作用の薬を購入できるんだな、この分野の薬は圧倒的に医療用医薬品のほうが充実しているな、高齢者がこのあたりのOTCを使っていたら注意が必要だな、などの大まかな知識が身に付きます。
臨床検査値ハンドブック
薬局にひとつあると患者さんの検査値でわからないことがあった時にすぐに調べる事ができます。
おわりに


薬の本はかなり値が張るけれど、立ち読みが難しい本が多いため、購入を躊躇する人が多いと思います。
実際私も何冊か買って無駄だったなと思ってすぐにBookOffに売ってしまった本もあります。
その中で自分の血肉になったなと思った本を紹介しました。
誰かの勉強の役に立てば幸いです。
転職に関する記事はこちら↓






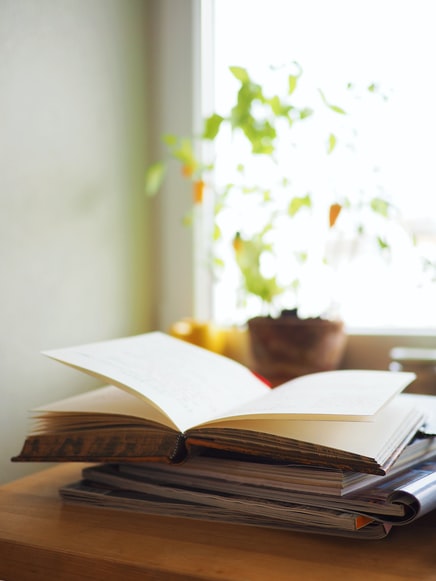
コメント