薬剤師の仕事は好きだし、楽しいけど、刺激が足りない…。もっと薬剤師の資格や知識を活かして何かしたいと思っている薬剤師の方は沢山いると思います。
小さな子供がいても、フルタイムで働いていても、好きな時間に、隙間時間に運営することができます!
この記事では、薬剤師が2年間ブログを運営し、110記事書いて得られたことを中心に、ブログの運営の始め方、費用、などをわかりやすく解説したいと思います。
ブログを始めたきっかけに関してはこちらの記事をどうぞ→自分の経験や知識が誰かの為になると嬉しい
- 薬剤師がブログを運営するメリット
- 薬剤師だからこそブログを通じて伝えられる情報
- 薬剤師のブログの始め方
- 収益化を狙うなら、狙わない方がよいジャンル
- 医療ライターの始め方
薬剤師がブログを運営するメリットとは?

何か楽しいことがある、メリットがあるなら、ブログをはじめてみようかな?
ほかのSNSにないブログの良さ
私はブログは資産だと思っています。
情報発信するツールには、Twitter、Instagram、Facebook、TikTokなど様々なSNSがありますが、ブログはストック型で、SNSはフロー型であると言われています。
ブログを書くことで自分の頭の中が整理される
紙に書いているうちに頭の中が整理されて、自分の目的や、やりたかったことなどがハッキリした経験はないでしょうか?
ブログを書くことも同じ効果があります。
ブログは人に見られることをどこかで意識して書くため、紙に書くときよりも丁寧にまとめよう、わかりやすく記載しようという意識が働きます。
そのため、頭にも残りやすく、紙に書いたときよりもきちんと頭の中が整理できます。
以下の状態の時は、ぜひブログに書いてみるといいと思います。
- 悩んでいるとき
- 頭が混乱して何をやっているのかわからなくなっているとき
- 知識がこんがらがってうまく整理できていないとき
薬の勉強することが楽しくなる
薬剤師は一生勉強をしなければならない仕事です。
薬の知識は最新のものに、常にアップデートしなければいけません。
仕事をしていてわからないことに遭遇した場合は、わからないままにせずに勉強しなければいけません。
 かばこ
かばこわかっていても、勉強するの嫌になるときあるんですよね…



最新の薬の知識は、わかりやすくまとめてアップすると、数か月後に人気記事になったりします。
アフェリエイトをすれば、収益化されることもある
最初に言ってしまうと、医療はアフェリエイトで稼ぎにくい分野です。



期待していた人、すみません。
私も稼げていませんし、医師ブログでも、ほとんどの人が医療分野では稼げないと公言しています。
YMYLジャンルはGoogleが厳しいガイドラインを設けており、基本的にはE-E-A-Tを満たしたサイトしか上位表示してくれません。
YMYLジャンルは、お金や健康など人生に大きな影響を与えるジャンルを指します。
EEATとは、以下のものを指しています。
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trustworthiness(信頼性)
YMYLジャンルで上位検索されるには、公的機関、総合病院、医薬品メーカーの順に優先され、次にクリニック、薬局などの企業が続きます。



素人よりはちょっとマシなレベルですね。
ただ、まったく無理というわけでもありません。
医療そのものというよりも、サプリメント、一般用医薬品、漢方、薬の飲み方の工夫、転職関係、おすすめ書籍など、少しずらしてアピールすると、上位検索される傾向にあるようです。



医師でブログで稼いでいる人は、「医師向けの投資関係の記事」や、「医師の視点での漫画考察」とか書いてました。
薬剤師で、一般用医薬品に特化したブログを運営している人もいました。



私自身は、飲みにくい薬の飲み方とか、薬の名称変更、医療ニュースは結構上位検索されてます。
Webライターをするときにアピール素材になる
医療分野の記事は専門性が高いため、最初の記事案件をとるハードルが高めです。
薬剤師などの医療資格があっても実績が何もない状態だと、まったく採用されません。
なおかつ、頑張って案件をとって記事を納品しても、実績としてポートフォリオに公開させてもらえないケースが多いです。
企業から声がかかることもある
私自身は、さほど運営も上手ではないため、執筆依頼、講演会の依頼などの大きなものは来たことはありませんが、取材や相互リンクの依頼などはきたことがあります。
日経DIで「薬局にソクラテスがやってきた」を連載し、「実践薬学」の書籍を執筆した山本雄一郎先生も、最初はブログがきっかけだったようです。



後輩の薬剤師に向けて、薬の知識を書いていたのがきっかけとどこかで読んだことがあります。



山本雄一郎先生にあこがれて、ブログを始めた薬剤師も多いようですよ!
山本雄一郎先生のTwitterはこちら↓
山本雄一郎先生の書籍、「実践薬学」はこちら↓
毎日の生活の刺激、やりがいになる
ブログに書いた記事が読まれていたり、メッセージをもらったりすると、やりがいや日々の刺激につながります。



薬剤師の仕事は、ルーチンワークになりがちで、たまにつまらなくなることがあるんですよね。
ブログ記事が読まれるようになるには、時間がかかることだけは注意を!
Abemaブログだと、書いてすぐに同じブロガーには発信されると思います。
しかしGoogleの検索エンジンでは、記事が掲載されてから、記事が認識されて上位表示されるまでに非常に時間がかかります。



半年くらいはかかるといわれています。
コツコツと諦めずに記事を書き続ける根気は、必要とされます。
薬剤師がブログを通じて伝えたい、広めるべき情報とは?


薬剤師だからこそブログを通じて伝えられることが絶対にあります。
薬剤師で仕事やプライベートで悩んでいる人、薬剤師になりたい人はたくさんいます。
薬剤師で知識を増やしたい人、一般のひとで、薬の効果、副作用、飲み方を知りたい人もたくさんいます。
薬剤師の日常業務に関する情報
薬剤師が何をやっているのか、外部の人にとっては謎めいているようです。
薬剤師は卒業するのはなかなか大変そうだけど、国家資格があって、安定している。
薬剤師になった後はどんなキャリアで、どんな仕事があって、日常生活はどんな風なのか?



もっと言ってしまうと、リアルな年収を知りたい人が多いみたいです。
薬学部を目指す学生さん、その親御さん、薬学部の学生さん、気になっている人はたくさんいるでしょう。
薬剤師の専門知識やトピックス
認定薬剤師や専門薬剤師などを持っている方は、ほかの薬剤師向けに薬の知識を情報発信してはいかがでしょうか。
投薬の際に患者さんに質問されたりしますよね?その際に調べ、わかった情報をブログで公開してはいかがでしょうか。
ひとりの患者さんが疑問に思うことは、ほかの患者さんも疑問に思っていることが多いので、日本全体の患者さんの役に立つと思います。
薬剤師のキャリア・転職に関する情報
薬剤師は他の業界に比べ、転職する人がおおい職種です。
薬局、病院、企業、他分野など転職の仕方も多岐にわたり、40代までは活発に動いている印象です。
転職エージェントのサポートが無料で受けられるとはいえ、無理な斡旋にあうこともあり、不安を感じている方が多いです。
転職の時の経験を、生の声としてブログに書くと、他の薬剤師の参考になるのではないでしょうか。
薬剤師が持つべきブログの目的とは?
アフェリエイトが目的でも、趣味が目的でも何でもよいと思います。
ブログを見る人にとって、医療や薬に関しては有益な情報を発信することが必要だと思います。



医療と薬以外は、素人なので、感想でも主観でも何でもいいと思ってますが…。



ブログを見てくれている人に、健康被害をもたらさないことは、医療従事者のモラルとして必要だと思います。
薬剤師のブログ運営のノウハウとは?


細かいことは、もっと詳しい方がたくさんいるので省きますが、ブログ運営に最低限必要なことを説明します。
ブログを始めるためのステップとは?
スマホで運営できなくもないですが、本格的な運営を考えているのであれば、パソコンは購入した方がいいでしょう。
まずは、どのブログサイトを選ぶかなのですが、自由度が高くアフェリエイトも今後考えているか、完全な趣味でやるのかで選ぶサイトは変わると思います。
自由度が高く、アフェリエイトも今後考えている場合
サーバーを借りて、WordPressで運営の一択だと思います。
このブログもConoha WINGでサーバーを借りて、WordPressでCocoonという無料テーマで運営していました。※WordPress自体はオープンソースソフトウェアのため、一切費用はかかりません。



2024.3~有料テーマのSwellを使用しています!


サーバーレンタル料は年間12000円程度で、WordPress簡単設立セット、バックアップ機能などが付いていて、用量も300Gと十分で、速度も速いため、おすすめです。
スマホのように、アプリのようなプラグインという機能があります。
昔はHTMLなども理解していないと運営が難しかったようですが、現在は私のようにまったくわからない初心者でも運営できるようにわかりやすくなっています。
長く使用する、本格的にブログを運営することを検討しているのであれば、WordPressがおススメです。
趣味でブログをやりたい
コメントが書きやすく、Abema内で交流を持ちやすいのが最大の魅力だと思います。
文字メインで書いていきたい場合はnoteやはてなブログ。
有料記事、無料記事などを分けて収益化を図りたい場合はnoteのほうがおすすめです。



じつは昔、Abemaブログをやっていました。
効果的なブログの書き方とは?
これも目的が何であるかによります。
Abemaブログのように、ブロガー同士での交流が目的であれば、主観、プライベートな情報をより多く盛り込んだ方がいいでしょう。
しかし、役に立つ記事を届けたい、Googleで上位検索されたい場合は、主観やプライベートな情報はなるべく減らさなければなりません。
また、書き方も工夫が必要です。私自身も最初はまったく意識していなかったので、偉そうに言えないのですが、2年以上運営して気が付いたことがあります。
- 目次を作る
- 見出しをつけてわかりやすく書く
- 結論から先に書く
- 最後にもう一度まとめる
- 医療関係の記事は、信頼できる1次情報のリンクを参考資料として載せる
読者のニーズに応えるための工夫とは?
これもはじめは意識せずに、好きなように書いていたので偉そうに言えないのですが、2年間運営して学んだことを書かせていただこうと思います。
読者が何に困っているのかをあらかじめ調べなければいけません。
具体的に説明すると、以下の2つのサイトで必ず検索されているキーワードを調べてください。
最初面倒で、全く使用していなかったのですが、好き勝手書いた記事はことごとく誰からも読まれず、むなしくなってきたので、使用するようになりました。



キーワードを意識して書いた記事は読まれているので、やはり最初に検索しないといけないと思いました。
薬剤師の副業にはwebライターがおススメ!
上述したように、ブログ運営とも非常に相性がいいので、同時に始めることもおすすめです。
おすすめサーバーはConohaWing、おすすめのクラウドソーシングサービスはクラウドワークスです。
私もこの2つを使ってブログ運営と副業をやっています。



ランサーズも初心者向けでよい仲介サービスのようですが、プロフィール写真掲載がネックで💦
ただ、その分詐欺案件は少ない、優良案件が多いとの話も聞いています。
Webライターはどんなことをする仕事か
各企業は、自社のサイトを検索エンジンで上位表示させるために、あらゆる施策をとっています。
そのひとつが、企業が自社サイト内で運営するコラム記事を充実させる方法です。



有益なコラム記事をたくさんあげると、企業のサイト自体も上位表示され、宣伝になります。
Webライターの仕事はほかにも色々ありますが、7割くらいの仕事は「企業のオウンドメディアへの記事投稿」であるといわれています。
長く続けていくと、校正、編集者、取材などの仕事も任せてもらえることもあるようです。
薬剤師の資格が活かせそうなジャンルはどんなものがある?
ここ数カ月見ていて、クラウドワークスで募集があった、薬剤師であることがアドバンテージになりそうなジャンルは以下のものです。
- クリニックに掲載する病気関係のコラム記事
- 精神医療関係のコラム記事
- 糖尿病関連のコラム記事
- 腸に関するコラム記事
- サプリメント関係
- 癌に関する記事
- 再生医療に関する記事
- ダイエット
- 美容医療
- 脱毛
- AGA
- 不妊治療
- 漢方
視野が広がる。薬剤師以外の仕事にも興味がわく
薬剤師以外にもプライベートの趣味で詳しいものがあれば、それもライターとしての強みになります。



薬局や病院で薬剤師をしていると、物を売る、顧客を意識する感覚があまりないため、新鮮です。
まずはWebライターとして、初めの一歩を踏み出そう!
最初の案件を獲得するまでは少し大変です。
大変だと感じる理由は主に以下の通りです。
- プロフィールを埋めるのが面倒
- クラウドワークスの仕組みがわからない
- 実績がないと採用してもらいにくい
- 詐欺案件が紛れ込んでいる
これらの解決方法は以下の通りです。
- ①はじめはタスクでクラウドワークスの仕組みになれましょう。
- ②他の売れてるワーカーのプロフィールを参考に、プロフィールを埋めてみましょう。
- ③勇気が湧いてきたら、ライター案件に応募してみましょう。
- ④評価が低いクライアント、実績が少ないクライアント、記号の羅列のような名前のクライアント、記事単価が0.1円以下の案件などは避ける



書けそうな案件に、どんどん応募してみましょう。初心者の単価はだいたい1文字0.5~1円程度です。



はじめは落ちまくりますが、皆そんなものなので、気にしないように!薬剤師転職案件は、詐欺案件が多いので、気をつけてください。



最初の文字単価は安いので、薬剤師の時給にはおよそ届きませんが、うまくライターとして成長できれば、薬剤師の給料を超えることも可能なようです。
私自身もまだまだもがいています。その経過はこちら↓


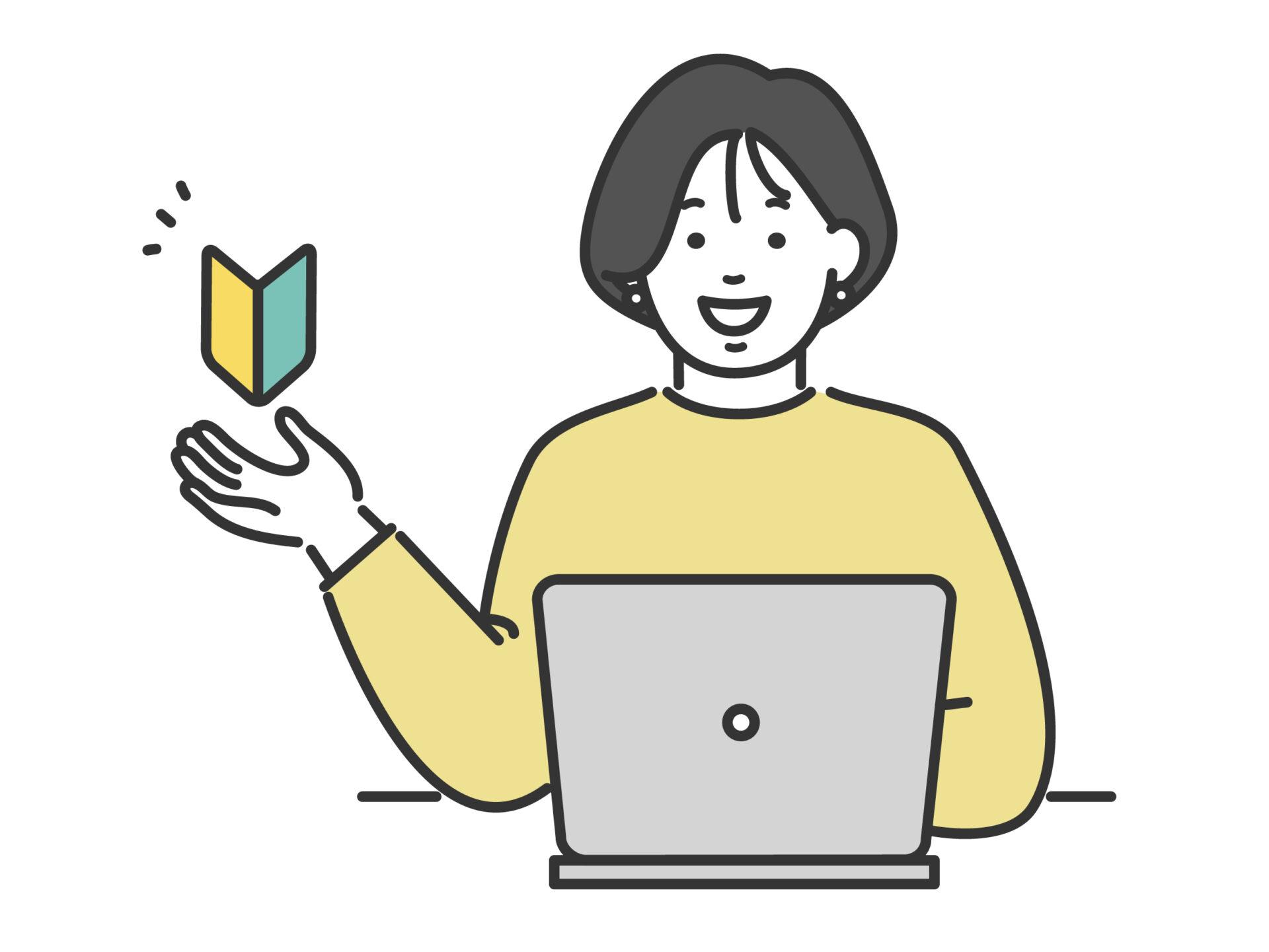
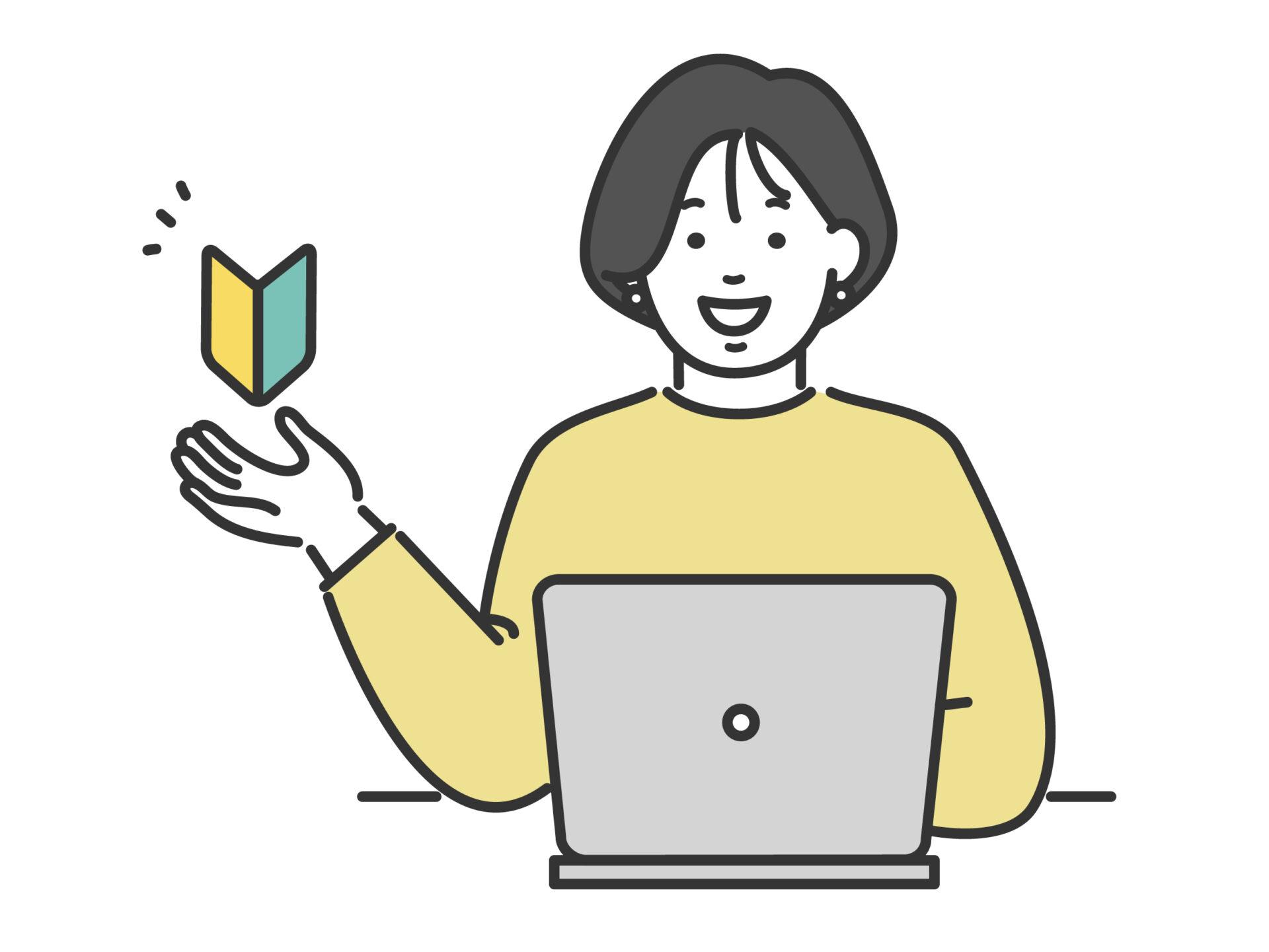
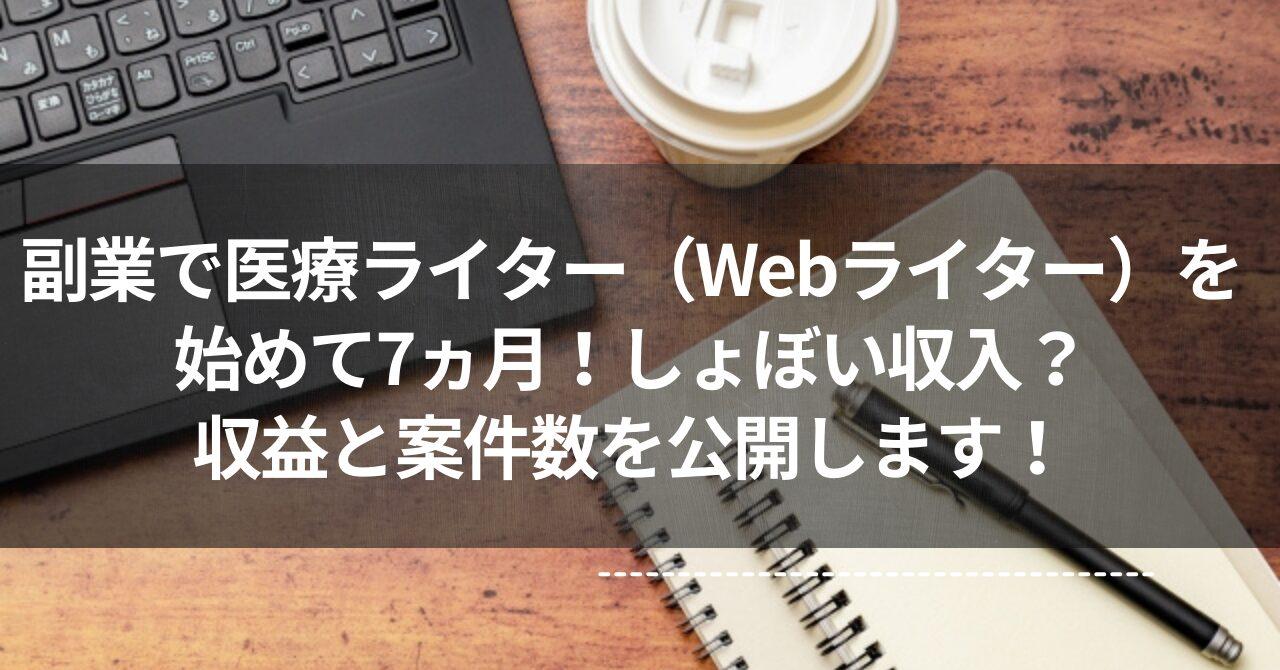
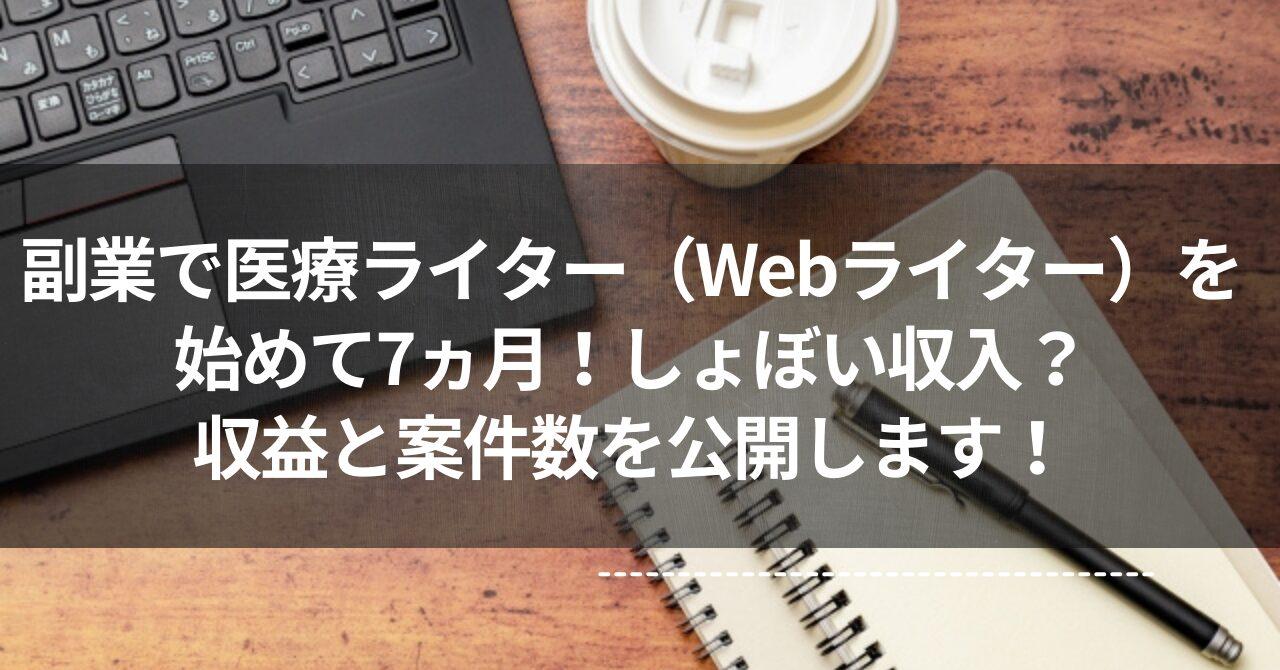
探してみると、ちょっと驚くとともに、自分にもできるかもと勇気がもらえます!
Webライターをやるなら読んでおきたい本!「文章起業」
おすすめ度★★★★★
月100万なんて、自分とは無縁だと思っていた(今も思っている)ので、役に立たない本だと思っていました。
はじめに読んでおけばよかったと思いました。
これから始める人は、ぜひ一度騙されたと思って読んでみてください。
著者の藤原将さんのTwitterはこちら↓
Webライターの基本を無料で学びたいなら、クラウドワークスの検定がおススメ!
クラウドワークスには、初心者ライター向けに、「クラウドワークス公式 webライター検定3級」という検定を無料で行っています。
動画も無料で視聴でき、合格すると、ワーカーのプロフィールに掲載されます。
これがなかなか無料だとは思えないほど、良い内容になっているので、是非チャレンジしてみましょう!
実際にチャレンジした記事はこちら↓


他にも取得した資格はこちら↓




まとめ





せいぜい時間とサーバー代くらいです。
途中でやめてもデメリットもありません。
もしも興味がわいたなら、まずは第一歩を踏み出してみることをお勧めします!

コメント