数か月後に病院への転職が決まっているので、今回が最後のトレーシングレポートになるかもしれません。
- トレーシングレポートとはどんなものか知りたい人
- トレーシングレポートの例を知りたい人
トレーシングレポート報告例

門前の薬局のトレーシングレポートは既にひな形が指定されており、それに従って記載するようになっています。
門前病院のトレーシングレポートのひな形に関しての公開は許可されていません。
報告例⑬ 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)によって動悸が出ている20代女性
甲状腺機能亢進症による動悸に、インデラルが処方されていたケースです。
薬剤:インデラル、メルカゾール、ヨウ化カリウム
朝食は食べないし、外出時忘れる、休みの日は昼まで寝てしまうんです。
インデラルの朝、昼の服薬が困難な状態です。
現在は100錠程度の残薬があります。
手の震えはないです。
動悸ってどんなものですかね?
 かばこ
かばこ長く罹患しているため、もはや動悸があるのが通常の状態になっているようで、「何が動悸かわからない」と言っていました。
朝食を食べない、外出時忘れる、休みの日は昼まで寝てしまうなど、インデラルの朝、昼の服薬が困難な状態です。
現在は100錠程度の残薬があるそうです。
ご本人が動悸がどういったものか認識できておらず、インデラルのコンプライアンス不良が動悸に影響を及ぼしているかどうかは不明です。
テノーミン(アテノロール)は1日1回の為、インデラルよりもコンプライアンス向上する可能性があります。
よろしければご検討ください。
テノーミン(アテノロール)はバセドウ病の頻脈に有効なようです。テノーミンの方がβ₁選択性が高いので、今回のように手の震えが出ていないケースではいいかもしれません。
報告例⑭ インスリンをきちんと打っているのに血糖が上がっていく50代女性
一部薬剤:ノボラピットフレックスペン、トレシーバフレックスペン
たまに液だれ、針が曲がる、インスリンキットの先が膨らんでいるときがある。
昼の打つ単位数が多めの為、少し親指が届きにくい。
インスリンボールができているかどうか自分ではわからない



2年前の開始時はHbA1c6.5程度のこともあったのですが、単位数を増やしているにも関わらず、徐々に数値は上がっていき(特にここ1年で顕著)、HbA1cが9.1まで上昇していました。
注射後に必ず針を取る事、曲がったら付け替える等の説明、インスリンボールが出来ている可能性があるので打つ場所をいつもの場所からずらすように説明しました。
ただ、液だれやキットの先が膨らんでいる事、親指が届きにくいことから斜めに打っていないか、最後まで打てているか、手技、針の付け替えなどに誤りがある可能性があります。
インスリンボールが出来ていないかの確認と合わせて院内で一度手技の確認をしていただくことは可能でしょうか。
ご検討をお願いします。
インスリンボールは明らかなものであれば、見ると一部膨らんでいるのでわかりやすいようですが、それ以外のものだと医師や他の詳しい医療スタッフが教えないとわかりにくいこともあるようです。
痛みは感じにくい場所なので、つい何度もそちらに打っている人もいるようです。
単位数が多いとフレックスペンは打ちにくくなる為、フレックスタッチを勧めてみるのもありかなと思います。(今回はスペース的にそこまで書けませんでしたが…)
外来でだめなら、教育入院のある病院に入院させて、インスリンの手技だけでなく、食事指導からしっかりやらないとだめかもしれないですね。
糖尿病療養指導ガイドブック
糖尿病療養指導士取得のための書籍のようですが、糖尿病の勉強がしたくて読んでいた本です。薬だけではなく、理学療法、栄養療法なども載っていて非常に勉強になって面白かったです。
報告例⑮ 少しでも薬を減らしたいけど、飲み忘れて薬が増えていく70代男性
一部薬剤:アジルバ、ボグリボース、ドキサゾシン、ジャディアンス※それぞれ食直前と食後で用法が分かれていました
昼、夕飲み忘れ多数あります。
食直前と食後で用法が分かれている事と外出時に忘れるためかな。
もう少ししっかり飲んで、よくなって、薬を減らしていきたいとは思っているのですが…



ボグリボースがあるため、食直前と食後に分かれてしまっています。
朝食後はかろうじて忘れないようですが、夕食直前と夕食後はどちらかを必ず忘れてしまうようでした。
夕の薬(アジルバ、ドキサゾシン)のみでも夕食直前に統一することは可能でしょうか。
「忘れそうな場合は食直前でも服用可」であることはこちらからもお伝えしました。
ご検討よろしくお願いします。
報告例⑯ 長期でクラリスロマイシン服用中の強いふらつき、倦怠感がある60代男性
一部薬剤:クラリスロマイシン ※ハルシオン、リフレックス、レクサプロ、プログラフ、チザニジンなど多剤服用中の患者さんです。
クラリスロマイシンはずっと飲んでますが、なぜ飲んでいるかはよくわかりません。



待合室で数分待っている間にも寝てしまい、歩行も頼りなく、非常に倦怠感があるように見えました。
ご本人様、クラリスロマイシンの服薬理由をご存じなく、疑義照会を提案しましたが拒否されました。
クラリスロマイシンが長期処方になっており、患者さんも服用意義を理解しておりません。
クラリスロマイシンのCYP3A4阻害作用は不可逆的で強い阻害薬に分類されます。
ハルシオン、リフレックス、レクサプロ、プログラフとの相互作用があり、特にハルシオンの鎮静作用等が強く出る可能性があり、禁忌ではありませんが注意が必要です。
レクサプロ、ハルシオン、リフレックス、チザニジン等鎮静、ふらつきが出やすい薬が複数出ているため、転倒にも注意が必要です。
クラリスロマイシンの継続の必要性に関してよろしければご検討お願いします。
クラリスロマイシンは昔からある薬で、耳鼻科等では少量長期で使われるメジャーな薬です。
ある抗がん剤で、添付文書上は禁忌の項目にCYP3A4を強く阻害する薬としか書いておらず、気になってクラリスロマイシンに関してメーカーに問い合わせたところ、禁忌であることが分かったことがありました。
メーカーは当然のように知っているだろうと思い記載を省いていることがありますが、現場の医師や薬剤師にその意識がなく、見過ごされているケースがあるように思います。
薬の相互作用と仕組み
しかし添付文書の内容だけではなく、なぜ添付文書の併用注意に上がっているのか、禁忌になっているのか、併用注意になっているもののなかでも注意が必要なものがあるという事を教えてくれた本でもあります。
★★★
報告例⑰ 高血糖症状の出ている可能性のある50代男性
一部薬剤:プレドニン5㎎(総量20㎎)
ステロイドの影響で高血糖の疑いあり。
検査値:随時血糖380㎎/dl HbA1c8.9%
目がぼやけている、足腰の脱力感、痺れあります。
頻脈(110回/分)があります。
喉の渇きはありませんが、たくさん尿がでます。
他薬の副作用でネフローゼ症候群を起こし、長期で入院した後に退院した患者さんでした。
腎臓内科の医師が院内ではインスリンを投与していたようですが、退院がきまったことで経口薬に切り替わっていました。
専門医でないため、退院後のインスリンのフォローまではできかねると判断したようでした。
退院直後の血糖値は100代まで下がっていたのですが、インスリンを中止し、経口薬に切り替えたことで再度上がってきてしまったようです。
6/10に上記症状を確認し、6/13に電話で体調悪化がないか再確認しました。
高血糖による視力低下、神経性症状(痺れ、脱力感、頻脈)の疑いがあります。
高血糖や症状が続くようであれば専門医のフォローが必要と思われます。
少なくとも目の症状は念のため早めの検査したほうがよいと思います。
また今後の骨折を防ぐために、骨粗しょう症のフォローもステロイド高用量の為よろしければご検討ください。
その後トルリシティを院内で投与、経口薬の増量、ステロイド減量があり、更に眼科検診もおこなったようでした。
結果としては加齢による白内障のみで高血糖による網膜症は起きていなかったようでした。
神経症状もだいぶおさまったようです。
その後ステロイドが7.5㎎まで減量になり、徐々に血糖も下がってきています。
ネフローゼ症候群になったのが薬の副作用の為なので、薬の追加には先生も慎重になっており、骨粗鬆症の薬は追加にはなりませんでした。
報告例⑱ 肝硬変の亜鉛補充にノベルジンがでた30代女性
一部薬剤:ノベルジン
ノベルジンの金額が高すぎてこのまま継続していけないかもしれないと不安です。
適応外ですが、亜鉛を補う薬にプロマック(ポラプレジング)という薬があります。
含有量が異なる為、単純な比較はできませんが、およそ1/8の値段で継続することが出来ます。
ご本人がかなり経済的にきついとのことでしたので、宜しければご検討ください。
亜鉛不足に適応が通っているのはノベルジンのみなので、先生は値段のことはあまり考えずに処方されたのだと思いますが。
しかし薬局で患者さんのカードを持つ手が震えていました。



いまはノベルジンのジェネリックがサワイ製薬から発売されています
その後無事にプロマック(ポラプレジング)に処方変更になり、問題なく継続されています。
ノベルジンとジェネリックの違い、プロマック(ポラプレジング)との値段や亜鉛の含有量の違いなどに関してはこちら↓


今回のトレーシングレポートの活用の仕方
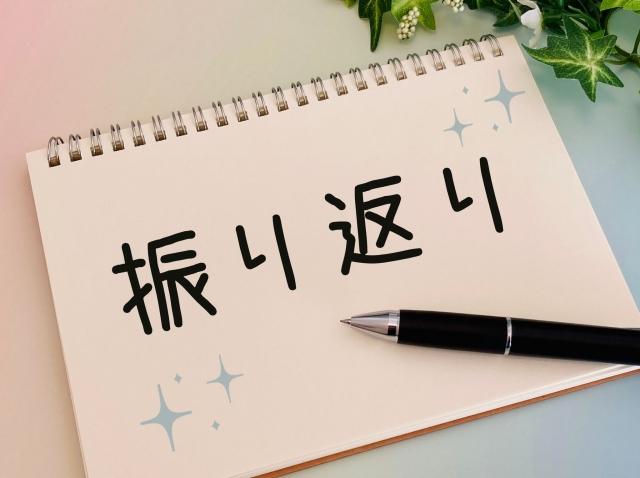
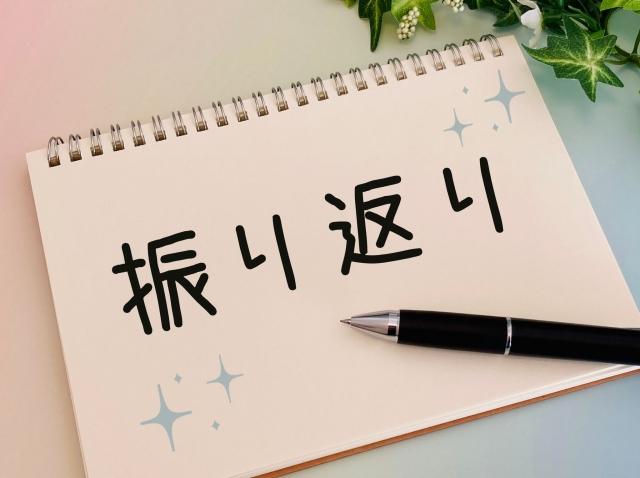
かなり処方変更もあり、こちらも書きなれてきたこともあり、やりがいを感じてきています。
医師本人からはあまり返答は返ってきませんが、役に立っていると感じると日々の仕事のモチベーションが上がりますね。
おわりに


薬局から病院に転職してしまうので、トレーシングレポートのような形での医師に対しての報告はこれで最後になってしまうかと思います。
違った形で、他の医療スタッフとのかかわりなどを報告していけたらいいなと思っています。
トレーシングレポートに関しては今まで3つほど記事を書いています。
こちらも良ければ参考にしてください。↓






コメント