私の働いている病院は糖尿病の専門病院の為、薬として扱う範囲は狭くなってしまいました。
しかしその代わりに薬のみならず検査や栄養などに関して学べる事が沢山あり、病気を全体として見ていく感覚が楽しいと感じています。
 かばこ
かばこ心臓内科の先生も来ているので、糖尿病その他成人病、心疾患の薬は扱っています。
メンタルやリウマチ、抗がん剤の併用薬チェック程度は行っています。
- 薬剤師の転職後が気になっている人
- 糖尿病専門病院がどんなところか気になっている人
- 糖尿病専門病院でのチーム医療やそれぞれの医療職の仕事を知りたい人
糖尿病は薬だけでは治らない!?糖尿病専門病院での治療とは?


総合病院の門前薬局で働いていた時は見えていなかったのですが、想像以上に糖尿病は普段の生活を個人の意識改善が必要な病気です。
糖尿病患者の数
糖尿病に罹患している人が1000万人、疑いのある人が1000万人、成人の6人に1人が糖尿病もしくは予備軍となっています。
透析導入の原因第一位は糖尿病です。
持続的な高血糖はかなり腎臓に負担を与えます。
糖尿病は食事、運動、本人の意識改革がすごく大切
定期的に丁寧な指導が入ったり、教育入院により自身の栄養バランス、生活スタイルが身体にあっていないことを学習することでかなり糖尿病は改善していきます。
メンタル疾患だったり、家族関係が複雑だったり、高齢で認知機能が悪化していて介入が難しいケースも沢山あります。
糖尿病を改善していく多職種の関り方


所属している病院では、医師を中心に、看護師、管理栄養士、薬剤師、検査技師がそれぞれ共通の糖尿病に関する知識を共有しながらそれぞれの専門性を活かしつつ外来、入院ともに患者さんのサポートに当たっています。



腎疾患(CKD)に関してもかなり手厚く指導が入ります
皆で指導内容を共有するため、下記のようなカードパスも利用して指導をおこなっています。
医師
糖尿病専門医、心臓専門医、泌尿器専門医がおり、必要に応じて連携をとっています。



糖尿病と心臓、腎臓、泌尿器、眼はかなり深い関わりをもっていることを入職して学びました。
看護師
主にインスリンの手技、指導にあたっています。
緊急入院時の対応、入院病棟管理もほとんど看護師さんの仕事です。



糖尿病になる人は高齢者が多いため、認知機能低下もあり、指導が大変そうです。
管理栄養士
糖尿病と栄養管理はかなり重要な結びつきがあるため、コメディカルの中で一番活躍しているのが管理栄養士さんだと思っています。
生活指導、薬物指導、運動の指導まで管理栄養士さんがやっています。そして説明の仕方がとても上手くてわかりやすいです!
教育入院中は普段の食事との違いを実感してもらうため、管理栄養士さんが提案したメニューで、適正なカロリー、塩分の食事をとってもらいます。
糖尿病、腎臓病をコントロールするための食事量、塩分量を実際に食べて理解することはとても大切なことです。



生活指導、薬物指導、運動の指導まで管理栄養士さんがやっています。
そして説明の仕方がとても上手くてわかりやすいです!
薬剤師
外来時の薬剤監査、疑義照会対応、様々な職種の人からの薬の質問、ワクチン管理、入院薬の準備、医師に対して薬に関して情報提供したり、勉強会セッティングなども仕事です。
検査技師
血液検査や生理検査などを行い、糖尿病の進行度合い、合併症(動脈硬化、視神経障害、神経障害、腎障害)の進行度合いを確認しています。
糖尿病専門施設として特有な検査項目は色々ありますが、頻繁に測定しているものとしては、抗GAD抗体、IRI、MCVなどでしょうか。
インスリンに対して自己抗体ができているかどうか、インスリンの分泌があるかどうか、神経障害が起きているかどうかなどを確認することが可能です。
糖尿病の薬の使い方
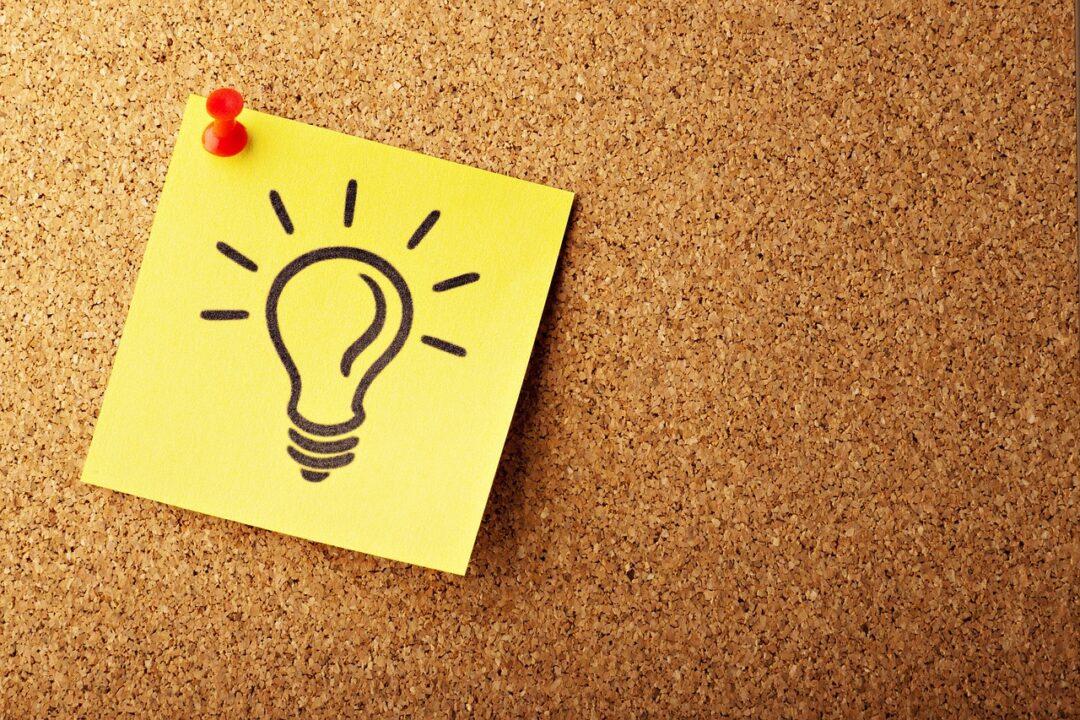
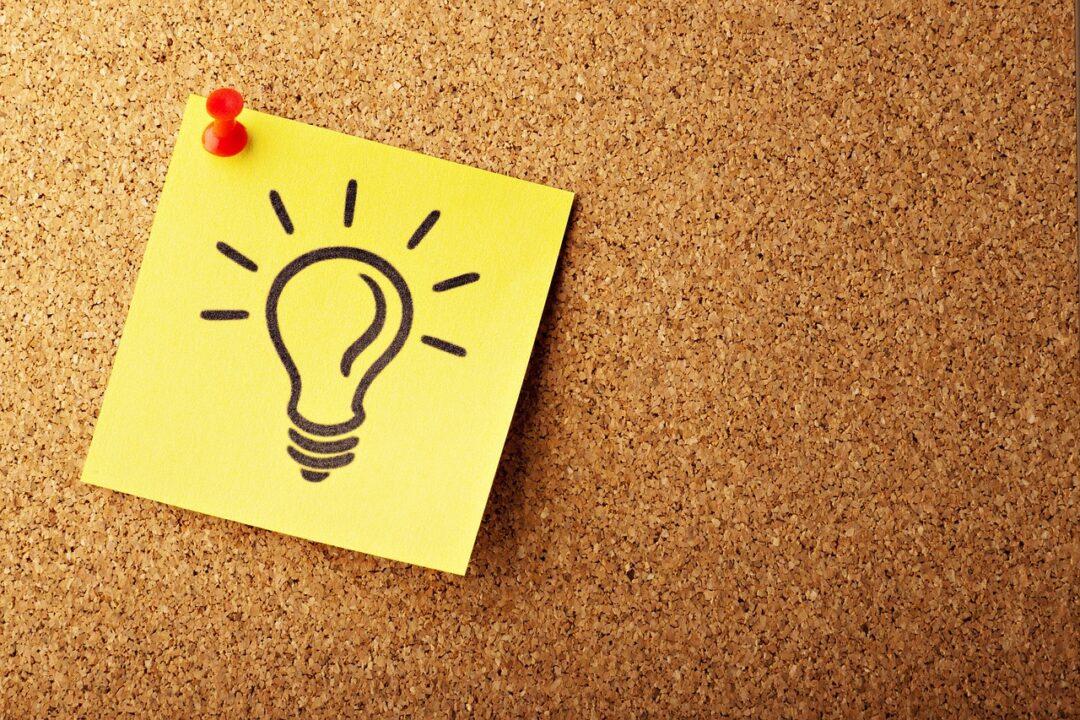
薬局で勤めていた時はそこまで深い処方意図があったとは知らず、転職してよかったな…としみじみ思っています。
糖尿病専門医ならではの処方
専門医ならではの糖尿病薬の使用方法を紹介します!
メトホルミンとツイミーグの併用
メトホルミンとツイミーグは作用も構造も似ている部分があります。
しかし専門医の間では全く別物という認識のため、インスリン抵抗性が高い人に併用されます。
ツイミーグはDPP-4阻害薬と類似の作用もありますが、DPP-4阻害薬との併用も問題ありません。
SGLT2阻害薬は1型糖尿病患者には慎重投与
1型糖尿病はケトアシドーシスを比較的おこしやすいです。
SGLT2阻害薬が、心疾患の予後をよくするため、循環器内科を中心にSGLT2阻害薬の処方が増えています。
オゼンピックは食欲を抑える目的で使用
教育や指導によって理解し、糖尿病をコントロールできればよいですが、ほかの疾患の影響や、薬の影響で食欲が抑えられない場合があります。
例えば、精神疾患で食欲が抑えられない人、SU剤で食欲が出ていた人に処方していました。
チアジド系は血糖を上げる事が多いので注意する
合剤にも入っているため、注意した方がよいでしょう。
メトホルミンはいい薬!しかし想像以上に下痢が多い
メトホルミンを中止するとHbA1cが上昇する場合が多いです。
乳酸アシドーシスはほとんど起きませんが、透析患者では起きることもあるようなので、腎機能がeGFR<30になったら禁忌、中止が無難です。
当院の医師は腎機能がeGFR<30になった場合は中止しています。
メトホルミンに関する記事はこちら↓


その他糖尿病薬以外の処方の仕方
ニフェジピン投与中の頭痛、肩こりで葛根湯長期処方のケース、ロサルタンに変えることで改善
ニフェジピンには副作用に肩こりがあります。
ニフェジピンの副作用は浮腫のイメージがありましたが、実際の臨床現場では、ニフェジピンによる肩こりに別の薬剤が足されている…、そんなこともあるようです。
ニフェジピンが高用量で処方されていて、葛根湯、エチゾラム、湿布などが追加されている場合は疑ってみてもいいかもしれません。
ニフェジピンに関する記事はこちら↓


糖尿病専門医がいる施設でとれる資格とは?
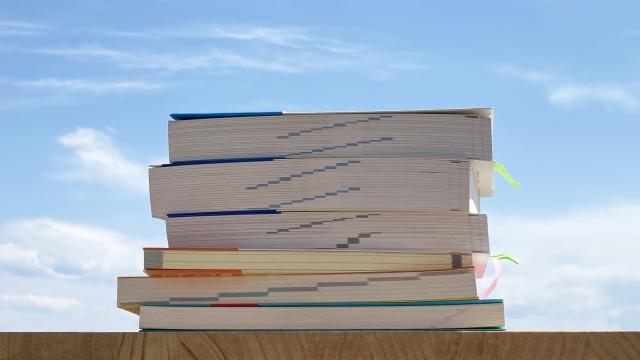
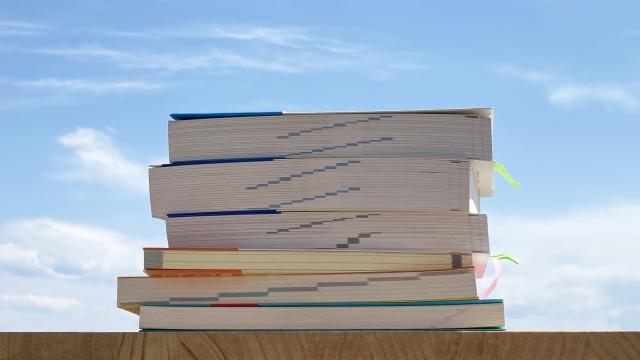
糖尿病専門医がいる施設で、コメディカルスタッフがとれる資格と勉強におすすめの書籍をまとめました!
おすすめ度は5段階評価で★~★★★★★までで表現しています。
糖尿病療養指導士(Certified Diabetes Educator of JAPAN :CDEJ)
糖尿病患者の療養指導に従事するコメディカルスタッフ(看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士※准看護士、栄養士は現在では不可に)に与えられる資格で、糖尿病専門医のいる施設で2年以上従事し、必要な症例を提出すると受験資格が得られます。
2020年7月時点で18774人の合格者がおり、2023年現在23回の試験が行われました。



年に1回しかないので、実質3年仕事に従事した後に試験を受ける人が多いみたいです。
入職前、入職後もテキストを使って勉強中なのですが、薬学以外の栄養学、検査、医学、理学療法に関しての出題が3/4くらいを占めているので、かなり知らないことが多いです。
私自身の受験は2年後なので、ゆっくり勉強していきたいと思っています。



検査、栄養、運動のところが薬剤師には馴染みがなさ過ぎて頭に入りにくいです。
糖尿病指導ガイドブック
おすすめ度 ★★★★★
まずはこれをしっかり読み込みます。
試験対策問題集 糖尿病療養指導のための力試し300題
おすすめ度 ★★★★
これも周りで受けている人は皆持っているようなので、ほぼ必須を言っていいと思います。
ところどころ問題文の誤りなどが目立ちますが、解説がかなり丁寧で、良い問題集だと思います。
地域糖尿病療養指導士(Local Certified Diabetes Educators :LDCE、Certified Diabetes Educators of Local :CDEL)
全都道府県でCDELが組織され、2020年7月時点で54団体となっています。
私の職場の事務さんは、ほとんど全員この資格を所持しています。
二つの資格の違いは?
知識量と受験資格、更新の必要性などの違いがあります。
| 資格 | 受験資格 | 難易度 |
| CDEJ | ・管理栄養士、薬剤師、看護師、理学療法士、臨床検査技師のみ受験可能 | ・就労条件、症例の提出、試験があるだけでなく ・必要な単位を取得したうえで更新を5年に一度しなければならない |
| CDEL | さまざまな職種の人が受験可能 | ・講習会受講で受験資格が得られることが多い ・試験問題は地域により様々(調べながら出来る試験のことも)で、更新の有無も地域による。 ・一般的に受験手数料、更新手数料はCDEJに比較して安価 |
費用がかかるため、取得を推奨している施設では、補助金として給料が上がるケースが多いようです。



当院でも2万円/月で給料が上がります。
おわりに)勉強不足を痛感する毎日


わからないことが多く、カンファレンスでは睡魔に襲われて、最後に怒られていますが、頑張ります!

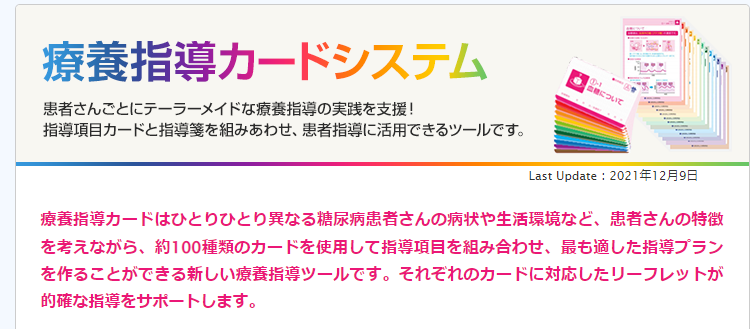
コメント