薬剤師ってこの先どうなるんだろう?薬剤師っていらなくなる?余る?
20年以上前から心配され、耳にタコができるぐらい言われてきたことではないでしょうか?
アメリカはさまざまな分野で日本の30年先を進んでいると言われています。
薬剤師の歴史に関しては、赤木佳寿子さんの博士論文『戦後日本における薬剤師職能の変容ー医薬分業の発達史の観点からー』を参考にさせていただきました。
 かばこ
かばこ細かい医療用語の説明は簡略化のため省かせていただいております。
ご理解いただけますと幸いです。
- 薬剤師に求められる役割の変容
- 薬剤師の歴史、医薬分業にいたるまで
- 医薬分業によって起きた変化
- アメリカの薬剤師の「現在」
- アメリカの薬剤師と日本の薬剤師の違い
- アメリカと日本のセルフメディケーション市場の違い
- 薬剤師の今後の予想(主観です)
医薬分業が実現するのに、100年もの時間がかかっていた


また、薬剤師法にも、第19条「薬剤師でない者は販売または授与の目的で調剤してはならない」と調剤の業務独占を規定しています。
医薬分業は1970年ごろに進展にはじめ、1990年に入ってから急速に進展していき、現在分業率は76.6%(2022年度)を超えています。
それでは、医薬分業が実現するまでの歴史をみていきましょう!
1874年 初の近代医療制度として公布された「医制」で完全な医薬分業を目指す方針が示された。
以下に「医制」の一部を転記します。
第41条 医師たるものは自ら薬を鬻ぐことを禁ず医師は処方書を病家に附与し相当の診察料を受くべし(略)
二等医師は願により薬舗開業の仮免状を授け調薬を許す
第55条 調薬は薬舗主薬舗手代および薬舗見習いに非ざればこれを許さず
但し薬舗見習いは必ず薬舗主もしくは手代の差図を受けその目前にて調薬すべし
医制より抜粋
ここからわかることは、文字通り読む限り医師の調剤は許されず、もし調剤するならば医師(二等医師)が薬舗開業の仮免状を受けて調剤しなければならかなったことになります。
つまり、調剤権は薬舗にしかなかったということです。
1887年 日本薬剤師会の前身、東京薬舗会の設立
薬舗主(後に薬剤師)が一致団結して医薬分業実施運動、および薬剤師の地位向上を行うため、1887年に東京薬舗会(のちの薬剤師会)の設立されました。
同時期に、この政治運動に触発され、大日本医師会(日本医師会の前身)の設立をいそいだという経緯があります。
※1891年(明治24年)に薬剤師会が法律改正案を提出依頼、明治期に6回、大正期に5回、昭和期に4回、44年にわたって計15回の嘆願を行い、戦後も医薬分業運動をつづけ、100年ぶりにやっとの思いで医薬分業が開始されました。



薬剤師会の涙ぐましい努力と、医薬分業がこんなに大変なことだったことを論文を読んで知って驚きました。
1889年 医師が附則によって調剤権を手に入れる
「薬品営業並薬品取扱規約」いわゆる薬律が交付されました。
ここで初めて薬舗から「薬剤師」という名称になり、薬品販売のみの薬種商と法制上の区分ができました。
第1条 薬剤師とは薬局を開設し医師の処方箋に拠り調剤するものを言う
※しかしこれには以下のような不足がつけられ医師の調剤が認められました。
附則43条 医師は自ら診療する患者の処方に限り、自宅において薬剤を調合し販売授与することを得(略)
薬律より抜粋
この附則は薬系関係者が「当分の間」という文言を入れるという条件でかろうじて認めた附則であったのに対し、公布された薬律には「当分の間」が削除されていたという経緯があったことが、ことさら医師と薬剤師の間の医薬分業に対する確執を生むこととなりました。
※さらにその後、附則であった医師の調剤は本則の但し書きに入り医師の調剤は正当化されたまま現在に至っています。
1914年 混合薬が法律違反となり、収入減を減らされる
処方箋に拠る調剤の需要がなかった薬剤師は売薬と普通薬の調剤(混合調剤)によって生計をたてていました。
しかし1914年におこった芝八事件の大審院最終判決(1919)では処方箋なしの調剤、即ち混合薬は薬律違反であるという判決がでました。
1950年代 薬剤師職能の空洞化
医薬品製造の工業化の進歩により、薬剤師の仕事が、薬の計量をすることから数を数える「ハサミ調剤」と呼ばれるような計数だけのものが残りました。
薬剤師の仕事が、「正確な薬を正確に準備すること」から「薬が人に投与されてからのことについて注意を向けるようになった」「医療の下請けでしかなかった薬剤師が医療に直接かかわるようになっていった」変化ともいえるのではないでしょうか。
1951年 医療分業法が制定
戦後GHQ公衆衛生福祉局長クロフォード・サムス准将が、日本において医療改革を行う際に、医療と医薬品販売を切り離す医薬分業を政策として打ち出しました。
そして、これを実施するために医薬分業法と呼ばれる法律が1951年に制定されました。
サムスはどのような考えをもっていたか
サムスは「医師が技術で報酬を得るべきで、物(医薬品)で儲けるべきではない」と考えていたと言われています。
医師は専門的知識に応じて報酬を得るべきであり、薬とか金とかのように医学的知識とは違うようなことは二の次ににすべきことであると主張していました。
主に以下の点を問題視していました。
- 国立レベルの医学部の卒業生と、医専と呼ばれる促進養成機関である医学専門学校の卒業生の二層の医師が存在すること
- 薬剤師が処方箋なしで劇薬を販売できていたこと、その一方で二流の医師が薬の調合や投薬をすることによって、生計のかなりの部分を得ていたこと
- 歯科医師が金を装飾用に患者に使用することで生計の多くの部分を稼いでいたこと
なぜ骨抜きの改革になってしまったか?
サムスは戦後の日本の医療福祉分野における非軍事化と民主化に力を注ぎ、数々の改革を実行しました。
薬学に関して主だった業績・政策は、製薬・医薬品産業の復興、薬学教育の改革、そして機能分業としての医薬分業を強制分業することでした。
サムスは日本で機能的分業を推進するために、米国薬剤師協会の使節団を招集し、全国を視察させ、その報告書によって日本政府に強制的機能的分業を勧告しました。
サムスの帰国を機に流れが一気に日本医師会側に急転し、サムスの意図した強制分業の実施はかなわないこととなったのです。
1958年 新医療費体系の開始
物と技を分離するためのサムスの理想とした新医療費体系が開始されました。
もちろん前述したように骨抜きの改革になってしまいましたが…。
本来技術の提供がその中心であるべき医療としてのその原価のおよそ1/4が薬剤費であり、英国に数倍する薬を使用しているといわれ、問題視されていました。
1961年 国民皆保険制度の開始
1950年代は市販薬でセルフメディケーションをおこなう人が4割ほどいましたが、国民皆保険制度の達成あたりから徐々に減っていき、さらに薬剤師は収入源を失っていきました。
大衆薬比率は1960年代の60.5%から1973年には20%に落ち込んでいきました。
また、このころから日本医師会長の考えが変わり始めます。
医師、歯科医師、薬剤師の三師会長が「医療制度の合理化達成、処方箋の発効促進のため三者は協力する」という文書に署名したのです。
当時の医師会長の武見の真意としては、医薬分業ではなく医師の技術評価の確立でしたが、そのために厚生省と戦うために、3者の足並みをそろえた方がよいと考えたようでした。
1967年 薬価基準の引き下げが始まる
当時はまだ診療報酬は不十分であることから、新医療体系に移行した後も医薬分業の話は進みませんでした。
1970年代 国民医療費が高騰
いわゆる薬漬け医療への批判が起こっていきました。
1974年 処方料の大幅な引き上げが行われる
技術料としての診療報酬引き上げを享受する代わりに薬価引き下げを受け入れているていくという形で結果的にものと技術の分離を受け入れていったと考えられています。
1990年以降
薬価差益はほとんど解消され、利益の出ない薬価となっていきました。
医師が薬で儲けることができなくなり、これ以上物と技術の分離を行う必要がなくなっていました。
1990年代以降、大きな病院からの院外処方箋が急増しました。
なぜ医薬分業は突然可能になったか


医薬分業がなぜ突然1990年を境に進展したのでしょうか?
医薬分業に関する医師会と薬剤師会の意見
100年にもわたって医薬分業に関して争ってきたことは前述したとおりです。
ここで、双方の意見に関してまとめました。
当時は医師会は医師への報酬が薬代込みである経済的な面も含めて、変化を拒む姿勢で医薬分業を否定していました。
医師会側(経済的な観点を指摘)
- 分業による診察料の徴収は患者の負担増につながり、貧困者が十分な医療を受けられなくなる
- 医師が薬を鬻ぐことは「善良なる習慣」であり、「社会の安寧秩序」である
薬剤師側(専門性の観点から指摘)
- 薬学は医学の余業として兼修できるものではなく、兼修できる余裕があればさらに医学をきわめるべきである
- 医学と薬学は修学の道が異なり、両業は個別の試験を経て開業が許されるべき
- 医薬品の良否、真贋の識別、分量の差異は人命の死生にかかわり、医師はそれに必要な学間に乏しい
- 医師が就学しない薬学を兼ねて本業でない薬価を収めるのは、自己の本分ではない報酬を社会にもとめるものである
- 責任分担による安全性の確保をすべきである
- 専門家が分担して行うことで、国民医療の質的向上を図ることができる。
- 薬剤師から十分な説明を受けることができる
- 欧米の大部分で実施されている
薬価差益が大幅に減少し、診療報酬が引き上げられた
医薬分業が大幅に進んだのは、法律の規定ではなく、経済的な誘導であったと言われています。
1967年以降に始まった薬価算定方式の見直しにより薬価差益が大幅に減少したこと、処方箋料の引き上げなど診療報酬のひきあげにより、経済的な誘導が行われました。
医薬分業によって起きた変化


私たち若手から中堅の薬剤師は、医薬分業になってからの姿しか知りません。
医薬分業でなかった時代との変化をまとめてみました。
処方箋によって薬の名前がわかるようになった
医師のいうことを素直に聞いていればよかった時代から、処方箋によって薬の名前がわかる、薬局で薬の名前がわかる、薬局で薬の説明があるというように、国民が自分で自分の病気やその治療法を知るという医療とのかかわり方の変化をもたらしました。



昔は、医師が何の説明もなく、患者は医師の言われたことを全面的に信じるほかなかったようです。
今では信じられないですが。



医師が信頼できない人であったとしても、患者さんは信じるほかなかったのですね。
ジェネリック医薬品への変更を容易にした
ジェネリック医薬品の変更の際、在庫問題、医薬品の商品名や一般名などの煩雑さ、数あるジェネリック医薬品の中からの採用検討といった負担が生じました。
薬剤費の比率は1960年代より下がっている
批判されていた薬漬けの影響も、医薬分業の影響か、医療従事者や医師の意識変化かの影響かはわかりませんが、減少しつつあるように感じます。
薬の安全性が保たれるようになった
病院の調剤所、院内薬局、第二薬局など経営母体が医療施設と同じ薬局(調剤所)は日本での「医薬分業」とはみなされていません。



処方内容の透明化による薬漬けの抑制、製薬企業からのマージン抑制、相互作用のチェックによって、かなり安全性があがっているのではないかと考えられます。
薬剤師の仕事の変化


医薬分業前と医薬分業後では、どのように薬剤師の仕事内容は変化していったのでしょうか?
物から人へ
「物から人を見る薬剤師にならなくてはならない」という点が、ここ数年の調剤報酬改定で着目されてきたポイントだと思います。
以下に赤木佳寿子さんの博士論文『戦後日本における薬剤師職能の変容ー医薬分業の発達史の観点からー』を参考に変化の表を作成しました。
- 物を見る:製剤→分析→調剤→ハサミ調剤
- 人を見る:医療者内での情報→医療者への・患者への情報
- 人と生活を見る(人間を見る):医療者・患者間での情報→患者の生活との接触・介入
また、アメリカから学んだDI、CP、PCという概念が少しずつ日本の薬剤師の仕事にも導入されていきました。
- DI(Drug information):薬剤情報提供(主に医療従事者に対して)
- CP(Clinical Pharmacy):薬物動態投与治療モニタリング(TDM)や薬剤情報提供、剤型の選択、投与方法の選択、量、一包化など、個々の患者さんへの安全適切な薬物治療を実践していくこと。
- PC(Pharmaceutical Care):患者のQOL改善といった患者の生活における目標に対して職務を遂行すること。在宅医療、減薬の提案、トレーシングレポート、投与後の介入などもその一部
| 年代 | 病院薬剤師 | 薬局薬剤師 |
| ~1950 | 物を見る | 一般薬の販売 |
| 1950~1970 | 人を見る(DI業務) | 一般薬の販売 |
| 1970~1990 | 人を見る(DI業務、CP業務) | 院外処方箋発行が始まる 物を見る(ハサミ)、(一部)人を見る(DI業務) |
| 1990~ | 人を見る(DI業務、CP業務) | 人を見る(DI業務) |
| 2000~ | 人を見る(DI業務、CP業務) 人間を見る(PC業務、チーム医療) | 人を見る(DI業務) 人間を見る(PC業務) |



アメリカの影響を受け、病院薬剤師が先に変化し、続いて少しずつ薬局薬剤師の仕事も変化しつつあることがわかります。
アメリカの薬剤師と日本の薬剤師の仕事内容の比較


アメリカはさまざまな分野で日本の30年先に進んでいると言われており、技術や制度など日本は数えきれないくらいアメリカの影響を受けてきました。
実際に、医療の分野も前述したように影響を強く受けています。
アメリカと日本では国民皆保険制度の有無の違いもあるため、まったく同じではありません。
アメリカの薬剤師と日本の薬剤師の仕事内容の違い(2023年現在)
年収に関しては、アメリカの薬剤師は約1300万、日本の薬剤師は約580万と言われています。
ただ、日本の薬剤師はアメリカの薬剤師よりも国民一人当たりの薬剤師数は2.5倍と推定されています。さらに物価やそもそもの平均年収(アメリカ:770万円、日本:546万円)も違うため、単純に比較はできません。
少し主観も入っていますが、アメリカと日本の薬剤師業務の違いに関して表にまとめました。
| 業務内容 | アメリカの薬剤師 | 日本の薬剤師 |
| 調剤業務 | × | ◎ |
| 監査業務 | ◎ | ◎ |
| 服薬指導 | ◎ | ◎ |
| 食事指導、運動指導 | ◎ | 〇 |
| 予防接種 | 〇 | × |
| リフィル処方箋 | ◎ | △ |
| 保険会社と協力して患者に必要な薬を提供 | 〇 | × |
| 調剤技師(Pharmacy Technicians)の監督 | 〇 | × |
| 記録の管理やその他の管理運営上の業務 | △ | ◎ |
| DI業務、CP業務、PC業務 | ◎ | 〇 |
高齢者の処方箋管理などに関しては、患者に直接アドバイスをすることもあるようです。
主な仕事内容は以下の通りです。年収は約352万円程度と言われています。
- 患者や医療従事者から処方薬を出すために必要な情報を引き出す。
- 処方箋に必要な薬の量を計測する。
- 処方薬をパッケージや容器に詰め、ラベルをつける。
- 在庫管理をして、薬や備品の在庫不足があれば薬剤師に注意喚起する。
- 処方箋支払いの受付と、保険給付支払手続を処理する。
- 患者の情報(過去の処方履歴含む)をデータとしてシステムに入力する。
- 患者からの電話対応を行う。
- 患者から薬や健康に関して質問がある場合、薬剤師に相談できる機会を調整する
日本とアメリカの大きな違いは、以下の3点ではないかと感じました。
- アメリカは薬剤師がほとんど調剤業務や在庫管理業務を行わないこと
- アメリカはワクチン接種やリフィル処方箋が浸透している
- アメリカは日本ほど国民皆保険が浸透しておらず、医療機関への経済的なハードルが高く、セルフメディケーションが充実している。
調剤環境の違い
日本の薬剤は、粉末や顆粒が多く普及しています。
医療保険制度の違い
アメリカは医療費が高額であることに加えて、低・中所得者層を中心に医療保険への未加入者が多いとされています。また、加入している保険によって受けられる医療サービスが異なるため、購入できる薬の種類や金額、受診できる医師や薬局まで制限が設けられています。
合理的な医療システムが構築されている一方で必ずしも平等に医療を受けられるわけではないという点が、アメリカの医療制度の特徴です。
2014年から開始した医療保険制度改革法(通称オバマケア)によって、2023年の医療保険加入者は1,600万人を超えるなどの進歩を見せつつありますが、医療を取り巻く環境は日本とはだいぶ違います。
アメリカには約6万件の薬局が存在し、そのうちの半数を数社の大手チェーン薬局が占めていると言われています。
Amazonの参入によって日本のような錠剤分包も増えつつあり、技術革新や社会変革が進むにつれて、さまざまな変化が起こっています。
市販薬、セルフメディケーションの市場は?
日本では処方薬として扱われている医薬品が市販薬やサプリメントとして販売されていたり、選択肢も日本よりも多く用意されています。
例えば、睡眠を助けるメラトニンというサプリメントやのど風邪に主成分はキシロカインという麻酔薬のスプレーが販売されています。
それでは日本のドラッグストア市場はどうでしょうか?
トータル人口が減少しても、ドラッグストアの主顧客である中高齢者市場は減少しないこと、高齢化社会になるほどヘルスケアニーズが高まること、現在38兆円の医療費高騰を抑制するためにセルフメディケーションの促進が必要なこと等が市場を広げる要因になっているからです。
薬剤師って余る?将来性はある?どうなる?未来の薬剤師(主観)
これまでの薬剤師の歴史や、アメリカの現在、日本をとりまく医療状況を考えると、以下のようになっていくのではないかと予測しています。
まず間違いなく起こるのが、以下の3つだと思います。
- 患者の保険負担割合の増加によって、医療費の患者負担の増加
- 更なるジェネリック医薬品の推進
- 製薬企業の淘汰



これだけ医薬品の出荷調整が続いているにもかかわらず、政府は薬価の引き下げを継続しています。
子供政策の財源を医療費に上乗せして徴収することも検討されています。
医療費を減らすため、薬剤師の仕事改革や市場拡大はおそらく近いうちに進むのではないかと考えています。
- ワクチン接種は医師以外の医療従事者でも行えるようにする
- リフィル処方箋の活用の推進
- 医療DXの活用の増加
- AIの発展により、疑義紹介業務が激減する



医師会の抵抗があるため、どこまで進むかはわかりませんが、すでに政府はこちらのほうに舵をきっています。
ここからは完全にわたしの考えですが…
上記から、薬剤師は仕事内容は変わるけれど、余ることはないと思います。
しかし薬剤師の数は確実に増えてため、今のような就職先を選び放題のような状況はなくなっていくのではないかと考えています。
ただ、残念なことに、薬剤師の仕事内容が変わっても、アメリカのように給料が増えることはなく、減っていくのではないかと予測しています。
将来性があるかどうかでいうと、微妙かな?というところです。
理由は以下の通りです。
- 日本の薬剤師の数はアメリカに比べて多すぎる
- 医療費高騰のため、医療従事者の給料は減らされる可能性が高い
- 日本の薬剤師が行っている仕事内容は、アメリカではテクニシャンが行っているものが多く含まれている(専門性が低い)
- そもそもアメリカと平均年収が異なる。アメリカと同じ国力にならないと同じ年収になることはない。
もしかしたら国の医療費財源とは別の、ドラッグストアの薬剤師だけは給料があがるかもしれません。
参考資料
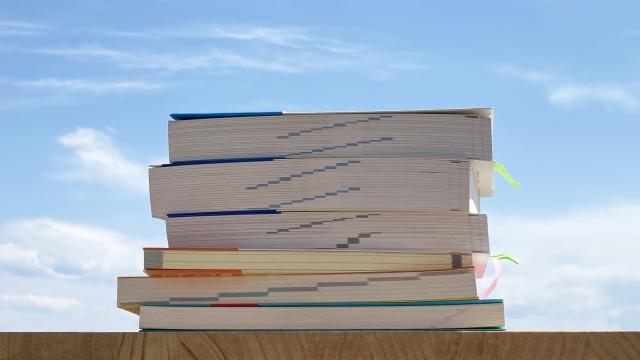
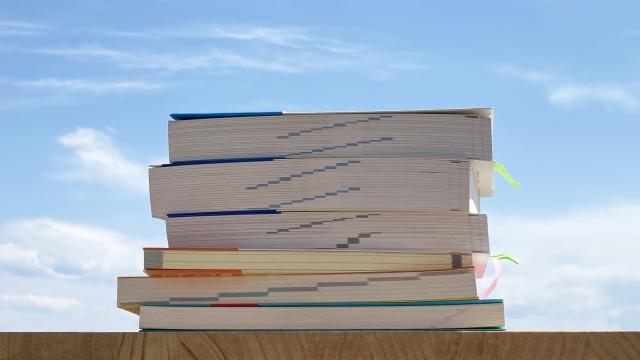
以下に参考にした資料を掲載しました。
最新AI産業の動向とカラクリがよ~くわかる本
おすすめ度 ★★★★★
1650円(税込み)です。
とても面白かったです。
図書館でずっと借りられていて読めなかったため、購入してしまいました。
AIを恐れるのではなく、理解して未来に備えたいと思わせてくれる本でした。
まとめ
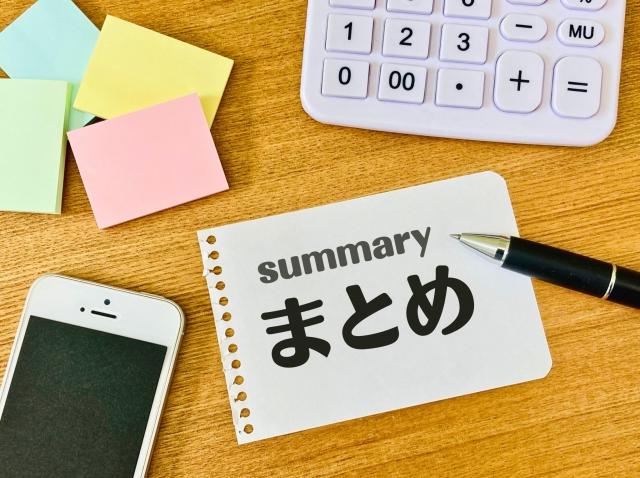
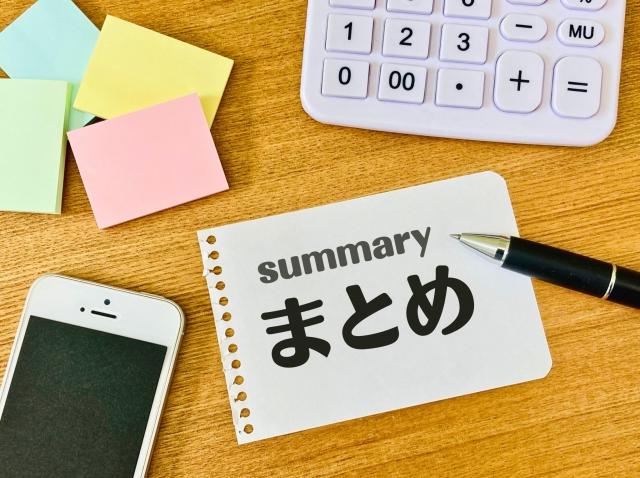
赤木佳寿子さんの博士論文『戦後日本における薬剤師職能の変容ー医薬分業の発達史の観点からー』を読み、是非内容を他の方にも知ってほしいという思いで、今回は短時間で読めるように要点のみをまとめ、記事にしました。
可能な限り、主観を交えず、論文の内容をそのまま抜き出しました。詳細を知りたい方は、是非論文を読んでみてください。
また、この記事では過去だけではなく、未来も調べたいと思ったため、アメリカを参考にしました。
未来に関しては完全な主観なので当たらない可能性もありますので、ご了承いただければ幸いです。

コメント