健康診断の胃カメラ検査でピロリ菌を発見された、胃薬をどんなに飲んでも胃が痛いと思って検査したらピロリ菌がいた…。
ピロリ菌の除菌をすることになった方に、今後処方される薬、検査、除菌率を上げる方法などをお伝えします!
特に除菌率を上げる方法、呼気検査前の注意点に関しては意外に知らない方が多く、投薬時に病院から聞いてないとよく言われるため、ぜひ実践してみてください!
- ピロリ菌とはどんな菌?
- ピロリ菌の除菌に使用される薬の効果、副作用、飲み方
- ピロリ菌の除菌効果をあげる工夫
- ピロリ菌の除菌後の検査とは?
ピロリ菌はどんな菌?
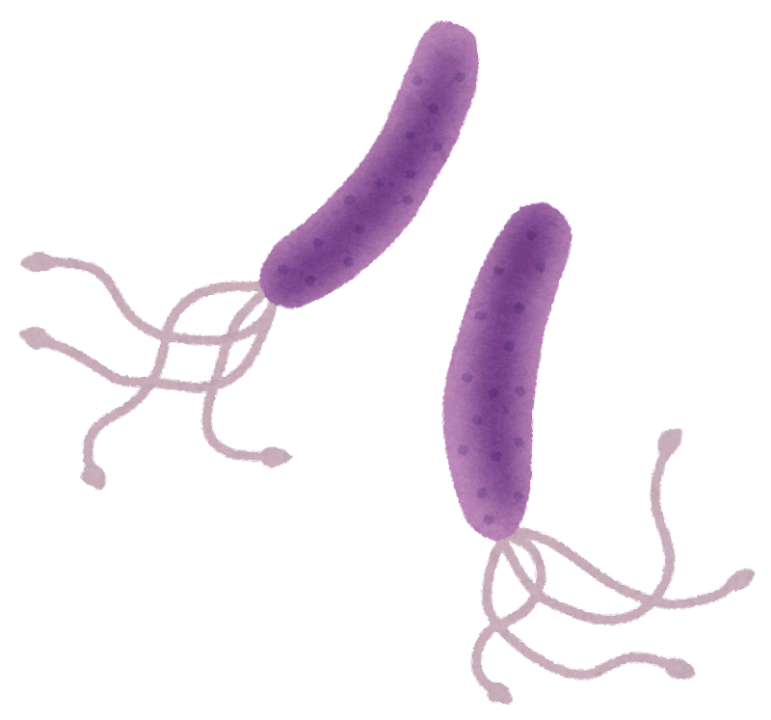
胃の内部は、胃液に含まれる塩酸によって、強酸性であるため、従来は細菌が生息できない環境だと考えられていました。
しかしピロリ菌はウレアーゼと呼ばれる酵素を産生しており、この酵素で胃粘液中の尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解し、生じたアンモニアで、局所的に胃酸を中和することによって、胃へ定着(感染)し続けることが出来ることがわかりました。
ピロリ菌にはどこで感染した?
じつは、どのような感染経路であるかはまだはっきりわかっていません。
上下水道の完備など生活環境が整備された現代日本では、生水を飲んでピロリ菌に感染することはないと考えられています。
また、大人になってからの日常生活・食生活ではピロリ菌の感染は起こらないと考えられます。
幼児期の胃の中は酸性が弱く、ピロリ菌が生きのびやすいためです。
そのため母から子へなどの家庭内感染が疑われていますので、ピロリ菌に感染している大人から小さい子どもへの食べ物の口移しなどには注意が必要です。
因果関係は不明ですが、投薬時によく聞くのが、「井戸水を小さい頃から飲んでいた」というエピソードでした。
発展途上国で多くみられることからもしかしたら多少の因果関係はあるのかもしれません。
ピロリ菌は 除菌しなくても大丈夫? 放っておくとどんな悪い事をするの?
子供の頃に感染し、一度感染すると多くの場合、除菌しない限り胃の中に棲みつづけます。
ピロリ菌に感染すると、炎症が続きますが、この時点では、症状のない人がほとんどです。
そのため、放置してもいいのではないかと思う人もいるかと思いますが、放置すると、面倒な病気にかかってしまう可能性があります。
ヘリコバクター・ピロリの感染は、慢性胃炎、胃潰瘍や十二指腸潰瘍のみならず、胃癌や MALTリンパ腫やびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫などの発生に繋がることが報告されているほか、特発性血小板減少性紫斑病、小児の鉄欠乏性貧血、慢性蕁麻疹などの、胃外性疾患の原因となることが明らかとなっています。
細菌の中でヒト悪性腫瘍の原因となり得ることが明らかになっている病原体のひとつです。
ヘリコバクター・ピロリ菌の陽性者では、陰性者と比較して胃癌の発生のリスクは5倍となるというデータもあるようです。
wikipidiaより抜粋
ピロリ菌の治療にはどんな薬が使われる?

「胃薬(PPI)+アモキシシリン(AMPC)+抗生物質」の3種類の組み合わせが一般的
商品名としてはボノサップパック400などがあります。
PPIとはどのような胃薬?
オメプラール、オメプラゾン(オメプラゾール)、タケプロン(ランソプラゾール)、パリエット(ラベプラゾール)、ネキシウム(エソメプラゾール)、タケキャブ(ボノプラザン) などがあります。
なぜ3種類の薬を一緒に飲む必要があるの?
抗生剤はピロリ菌の増殖時に殺菌作用を発揮しますが、ピロリ菌はPH≦5ではほとんど増殖しません。
そのため胃酸の分泌をこの薬でしっかり押さえる必要があるのです。
なぜ2種類の抗生剤を飲むの?
どんな副作用がでる?ほかにも注意することは?
3種類の薬を使用するため、それぞれの薬の副作用があらわれます。
一番多い副作用は下痢
抗生剤、胃薬共に副作用として下痢が報告されています。
ボノサップパックでは下痢が10.6%に報告されています。
臨床研究では、ミヤBMを除菌の1週間前から投与すると、除菌率が75%→91%に上昇した報告があるそうです。
またヨーグルトでも同様の報告が上がっています。(日経メディカル記事参照)
口内炎、味覚異常にも注意を!
口内炎、味覚異常(2%)があらわれることがあります。
アレルギー反応にも注意!
抗生剤は全体的に薬剤アレルギーが出やすい薬ではありますが、中でもアモキシシリンは比較的多く報告されているため、副作用歴がないかどうか確認してください。
併用薬にも注意を!
併用薬を薬局で必ず確認してください。
副作用が出たらやめてもいい?
途中でやめてしまうと除菌率が落ちる事は避けられません。
薬によるピロリ菌の除菌率はどのくらい?
薬剤によって差があります。
1次除菌に用いる薬剤に関して説明すると、
「ボノサップパック400」 に含まれるPPI(タケキャブ)はそのような影響を受けにくい為、除菌効果は90%以上になると言われています。
保険適応で何回までチャレンジできる?
1次除菌(1回目の除菌)
タケキャブ(PPI)+アモキシシリン(AMPC)+クラリスロマイシン 商品名: 「ボノサップパック400」、「ランサップ400」
2次除菌(1回目で失敗した場合の除菌)
PPI+ アモキシシリン(AMPC)+ メトロニダゾール
3次除菌(1回目、2回目ともに失敗で、3回目)(自費)
高用量のPPI+高用量の アモキシシリン(AMPC) +レボフロキサシン(クラビット)もしくはシタフロキサシン(グレースビット)を用いることが一般的です。
 かばこ
かばこ3次除菌までいっている人は薬局に来る患者さんではみたことがありません。
薬を飲み忘れた場合はどうすればいい?
基本的には飲み忘れないで飲んでください。
空腹時に飲むと、胃が痛くなる可能性がある(既にピロリ菌の影響で弱っていると考えられる)ため、出来れば食後、多めの水で服用しましょう。
ピロリ菌の除菌時の注意点!除菌効果を上げて1回で除菌を終わらすために


できれば1度の除菌でピロリ菌とさよならしたい方がほとんどだと思います。
そんな人のために、ピロリ菌の除菌率をあげる工夫を解説します!
酒とたばこはピロリ菌の除菌率を落とすのでがまんを!
どの程度はか不明ですが、お酒も影響を及ぼすと言われています。
たった7日間の事なので、刺激物、飲酒、喫煙は我慢できるといいですね!
7日間忘れずに薬を必ず服用しよう!
服用を忘れてしまうと除菌効果が落ちる事は避けられません。
ピロリ菌の除菌後の検査はどんなものがあるの?


ピロリ菌が除菌できたかどうかはどうやってしることができるのでしょうか?
検査内容を詳しく見ていきましょう!
ヘリコバクター呼気試験
一番利用されている方法で、除菌後4週以上後に行うことが多いです。
ピロリ菌に感染していると、そのウレアーゼによって胃内で尿素がアンモニアと二酸化炭素に分解されて、呼気中の二酸化炭素における 13Cの含有量が、非感染時より大きく増加するため、間接的な診断ができます。
呼気検査前は抗生剤、胃薬は飲まないように。
呼気検査前(できれば2週間前から)は抗生剤、胃薬は飲まないように気をつけてください!
検査結果に影響を与えないために服用しないように注意してください。



ほかの医療機関を受診する場合は、ピロリ菌検査前であることを忘れずに伝えましょう!
血中・尿中抗H. pylori IgG抗体検査
ピロリ菌に感染すると、本菌に対する抗体が患者の血液中に産生されます。
血液や尿を用いてこの抗体の量を測定し、ヘリコバクター・ピロリ抗体(血清Hp抗体)が高値であればピロリ菌に感染していることが認められます。
ピロリ菌感染の有無を検索するスクリーニング検査として簡便であるため、広く行われている方法です。
尿を検体とする場合は、20分の迅速検査で判定が可能です。
検査をおこなう場合は除菌後6か月以上経ってからとされています。
便中H. pylori抗原検査
診断や研究用途に作られたピロリ菌に対する抗体を用いた抗原抗体反応による検査です。
この抗体が、生きた菌だけでなく死菌なども抗原(H. pylori抗原)として認識し、特異的に反応することを利用し、糞便中H. pylori抗原の有無を判定します。
非侵襲的に本菌の存在を判定できるという長所があります。
除菌後4週くらい経ってから行います。
内視鏡生検検査
内視鏡検査で胃炎を指摘されている場合には除菌後に内視鏡検査を行うこともありますが、基本的には行わないことが多いようです。
非侵襲的な検査と合わせることでより正確なデータが得られます。
迅速ウレアーゼ試験
キット迅速ウレアーゼ試験 (rapid urease test, RUT)尿素とpH指示薬が混入された検査試薬内に、内視鏡的に採取した胃粘膜生検組織を入れます。
胃生検組織中にピロリ菌が存在する場合には、本菌が有するウレアーゼにより尿素が分解されてアンモニアが生じます。
これに伴う検査薬のpHの上昇の有無を、pH指示薬の色調変化で確認します。
この検査によってピロリ菌の存在が間接的に診断できます。
組織鏡検法
組織切片をHE(ヘマトキシリン-エオジン)染色あるいはギムザ染色により染色し、顕微鏡で観察します。
直接観察することによりピロリ菌の存在を診断できます。
また、培養不能でウレアーゼ活性ももたないcoccoid form(球状菌)の状態でも診断できるという長所があります。
培養法
胃生検切片からの菌の分離培養によって、ピロリ菌の存在を確認します。
この検査法の長所は、菌株を純培養し入手できる点であり、欠点は、本菌は増殖速度が遅いために培養には3日から7日を要するため、この検査法をとると時間が掛かる点です。
まとめ
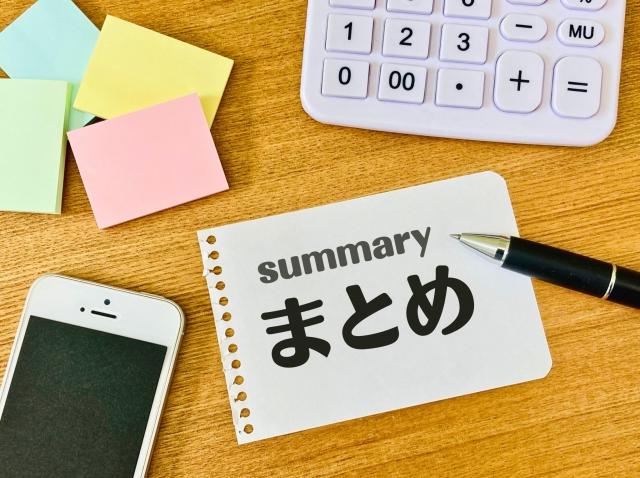
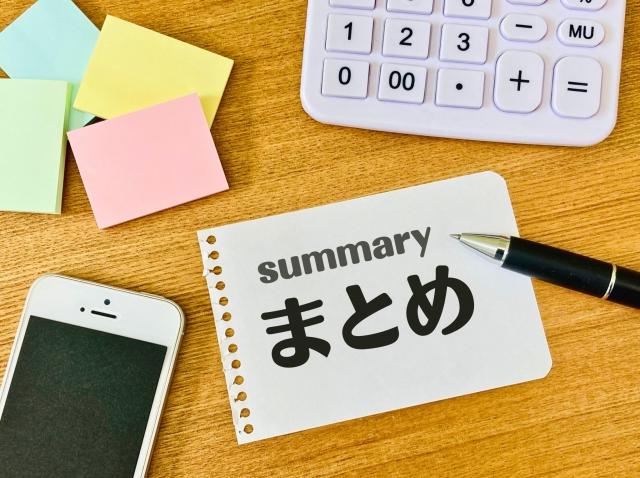
かなり優秀な薬の開発により、ピロリ菌は以前よりも除菌率が上がっています。
しかし間違った飲み方をすると2回目、3回目(自費)と回数を重ねてしまうこともあるため、1回で確実に終わらせるために、除菌率を上げる為にできるをまとめました。
特に喫煙、お酒が影響出ること、検査前に胃薬、抗生剤、整腸剤は飲まない方がよいことを知らない方が多かったため、この記事を書きました。
よければ参考にしてください。
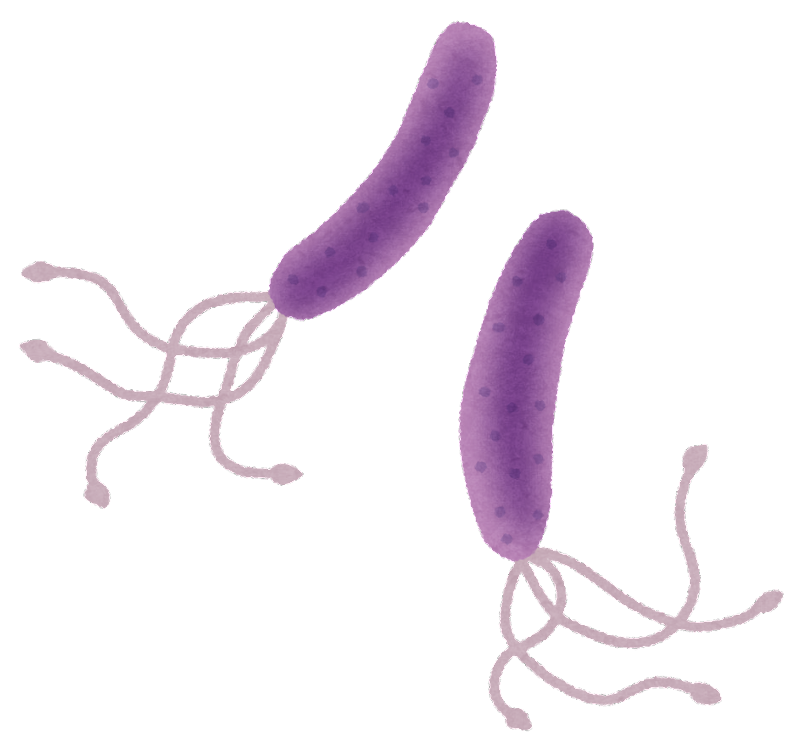
コメント