腎機能が落ちていることに気がつかずに、先生からある日突然指摘されてびっくりする人も多いのではないでしょうか?
薬局で途方に暮れている患者さんによく遭遇します。
腎臓病の方への贈り物で困っている方はこちら↓

- どんな食事をとったらいいか
- 食事療法は効果があるのか
- お勧めの市販の商品は?
- 運動療法でおすすめは?
腎臓病とは?慢性腎不全(CKD)とは?
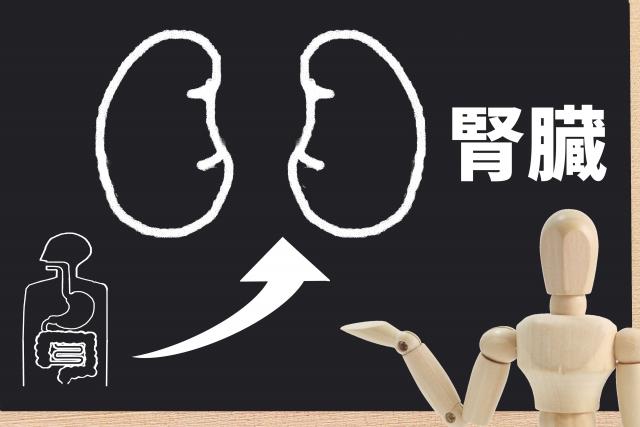
腎臓病は、腎臓の糸球体や尿細管が冒されることで、腎臓の働きが悪くなる病気です。
腎臓病にはさまざまな種類があり、それぞれの原因や症状も異なります。
腎臓の機能はいちど失われると、回復することがない場合が多く慢性腎不全(CKD)といわれる病態になります(急性腎不全の場合は機能が回復することもあります)。
現在、日本には約1,330万人のCKD患者がいるといわれています。
これは成人の約8人に1人にあたる数です。
人工透析をうけている患者さんも、26万人を超えており、その数は毎年1万人ずつ増え続けています。
医師は検査値のどこを見て腎機能を判断している?

血液検査の項目で言うと、血中尿素窒素(BUN)、血清クレアチニン値とeGFRという項目、病院によってはCCr(クレアチニン・クリアランス)という項目を見ています。
また、尿検査では尿たんぱくが検出されてきます。
どのくらい数値が落ちると、要注意と言われるか
既往や尿たんぱくの有無、年齢にもよるため、一概には言えませんが、eGFRもしくはCCrが40未満になると要注意と言われ、食事内容の見直しを提案されているケースが多いです。
腎機能は一時的に悪化する場合もあり、気にしなくてよいケースもあります。
以下に例をまとめました↓
- 脱水傾向
- 一部の薬では、一時的に腎機能の悪化がみられる
- 糖尿病が改善し、糖の排泄が減った時も一時的に腎機能が悪化してみえることがある
腎臓の機能が落ちてくるとどんな問題がおきる?

腎機能の低下がかなり進行すると、吐き気や食欲不振、むくみ、かゆみ、皮膚の色素沈着、呼吸困難、高血圧など尿毒症と呼ばれる症状が現れ、けいれん、感覚の喪失、手足のしびれなどの神経症状のほか、 心臓病や脳卒中 、心不全、肺水腫など致命的な合併症も懸念されます。
また、骨がもろくなるため、骨折なども起こしやすくなります。
腎臓はどのくらいのスピードで悪化する?
腎臓は25歳時点では、90~100ml/分あるといわれています。
25歳を過ぎるとCCr(クレアチニンクレアランス)もしくはeGFRは1.0%/年の割合で低下するといわれています。
80歳の高齢者であれば35~45ml/分くらいまで落ちているのは、生物学上、仕方がないということですね。
腎臓の機能が落ちる原因は?薬、病気の影響は考えられる?

腎機能が落ちる原因は何でしょうか?
加齢以外に薬の影響や病気の影響は考えられるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう!
腎障害をおこす病気、生活習慣
腎障害をおこす病気としては、糖尿病や慢性糸球体腎炎(蛋白尿や血尿が長期間持続する病気)が考えられます。
肥満や運動不足、喫煙、ストレスなどからくる高血圧症、高脂血症などのメタボリックシンドロームも腎臓に負担をかけ、腎機能の低下に大きく関与しているといわれています。
そのほかとして遺伝も考えられています。
腎障害をおこす可能性がある薬
薬剤性腎障害を頻繁に発症させる薬物としては、抗菌薬、 NSAIDs が最も多く,併せて 60∼70 %を占めるという報告 があがっています。
そのほかに造影薬、抗癌薬、抗リウマチ薬、レニン・アンジオテンシン系(RAS)阻害薬、抗ウイルス薬、抗てんかん薬などがあげられています。
このうち注意が必要なのがNSAIDs といわれる痛みとめで、市販で販売されているため、気軽に手に入れることができます。
心配な場合は、痛みとめを購入時に必ず薬剤師に相談するようにしてください。
腎臓によい食事とは?どんな食事をとったらいいのか?水の制限は必要?

食事療法の基本は以下の通りです。
- 水分の過剰摂取や極端な制限は有害
- 食塩の摂取量は基本は3g/日以上6g/日未満
- 肥満の改善に努める
- たんぱく質の制限(0.6~0.8g/㎏/日)
- カリウム高値であればK制限
- 性別、年齢、運動量を加味して、30~35kcal/kg/日(肥満の糖尿病では20~25kcal/kg/日も可能)
- 適正飲酒量はエタノール量として男性では20~30ml/日(日本酒1合)以下、女性は10~20ml/日以下
(やさしい慢性腎臓病の管理 改訂4版 参照※現在は絶版になっています)
詳しレシピのおすすめはこちら「ウェルネスレシピ」
食事療法は腎臓の悪化を防ぐのに効果がある?
食事内容を改善することは腎機能の悪化を防ぐのにかなり効果があります!
一度落ちてしまった腎機能を改善することは難しいですが、腎臓機能の悪化を鈍化させることは食事療法で十分に可能です。
実際に薬局で担当している患者さんでは、食事療法を頑張っている方は10年くらいたっても腎機能の低下があまり見られませんでした。
※個人差があること、腎機能の悪化の程度によるため、透析などを検討する段階にいる方は医師の指示に従ってください
腎臓によい、おすすめのの市販の商品、宅配サービスは?
塩分がどうとか、たんぱく質がどうとか色々言われてもさっぱりよくわからず、このままだと何も食べるものがなくなってしまうと途方にくれてはいないでしょうか?
ネットや本で見ても色々書いてあってよくわからないですよね?
糖尿病を併発している場合には、教育入院を行っている病院もあるため、探してみるとよいでしょう。
教育入院では、糖尿病の知識のみならず、腎臓に関して、食事に関して丁寧に教えてくれます。
さらに、実際に栄養士さんが作ったメニューを食べてみることで、どんな食事をとればよいのかの参考にもなります。
教育入院に関してもっと知りたい方はこちら→糖尿病教育入院ってなに?
腎障害の人にお勧めの宅配サービス
宅配サービスは色々ありますが、普通の人向けや成人病向けのサービスが多いです。
腎障害を指摘されている方はその病気を考慮した宅配サービスを頼んだ方が、今後どのような食事を作ったらいいのかの具体的なイメージをつかみやすいと思います。
メディカルフードサービス株式会社
介護向けの柔らかい食事なども扱っています。
お試しセットもあるので、味がどうか気になる方でも、気軽に始めやすくなっています。
ウェルネスダイニング株式会社
こちらは弁当の宅配のみならず、スープや半完成品(後は少し焼いたりするだけ)なども扱っており、イメージがさらにつかみやすくなっています。
また、レシピなどもサイトには載っているため、こちらの宅配サービスでイメージがつかめたら、レシピを見ながら色々チャレンジしてみるのもいいかもしれませんね。
腎障害の方におすすめの市販の商品
調味料など、腎障害のひとにおすすめの商品を紹介します。
腎臓病の方向け減塩調味料セット
私の義父が腎臓病なため、夫から言われて実際にこちらを年に2回購入して送っています。
味もいいようです。

初回の方向けにお試しセットもあります

キッセイゆめシリーズ レトルト
宅配サービスは料金的にも敷居が高いという方はレトルト食品も販売されています。
これでも十分イメージはつかめると思います。

腎臓の悪化を防ぎたい!家庭でできる簡単な工夫は?

腎臓の機能が落ちた人におすすめな、普段の生活にとり入れられる簡単な工夫を伝えたいと思います!
減塩しつつ「おいしく食べる」工夫を教えます!
- うま味:天然だし(昆布、削り節、干し椎茸など)のうまみや味の素を利用する
- 香ばしさ:薄い味付けでも、焼き立て、揚げたての香ばしさで美味しく食べる
- 香辛料:スパイス、ハーブ、生姜、にんにく、こしょう、わさび、からし、七味、トウガラシなどを使う
- 酸味:酢、レモン、ゆずなどの柑橘系、トマトなどの酸味を使う
- 塩分と甘味は一緒に減らす:塩や醤油の量を控えるときは、砂糖やみりんも一緒に減らす
- 味は食品の表面につける:塩味は舌に触れたときに感じる為、下味を付けるより、食べるときに調味して表面に味を付けるようにする
(やさしい慢性腎臓病の管理 改訂4版 参照※現在は絶版になっています)
最近は小学校の給食もものすごく減塩されています。
腎臓に負担!たんぱく質を減らすコツ
低タンパク質食を効率よく実施するためには、摂取たんぱく質の6割以上を肉、魚、卵などの動物性たんぱく質でとるようにします。
さらに米の中に含まれるたんぱく質を減らすため、低たんぱくご飯やでんぷん製品を取り入れた食事療法を実践します(やさしい慢性腎臓病の管理 改訂4版 参照※現在は絶版になっています)
主食(パンやごはん)を低たんぱく食に抑えることがポイントです。
そうすれば主菜(おかず)の肉類の減量を少なくすることができ、一般的な食事とあまり変わらない献立にすることが出来ます。
腎臓に負担!カリウム(K)を減らすコツ
カリウム(K)は多く含まれる食品のとりすぎに注意し、調理方法を工夫することで減らすことが可能です!
1.カリウム(K)の多い食品を控える
以下の食品のとりすぎに注意しましょう!
- 果物(バナナ・メロンなど)、ドライフルーツ
- イモ類
- 野菜類(ほうれん草、カボチャなど)、乾燥野菜(切り干し大根、野菜チップス)
- 豆類・ナッツ類・海藻・緑茶・100%ジュース・野菜ジュース・青汁など
2.調理の工夫でカリウム(K)を減らす
カリウム(K)は水にとけやすい性質があります。
(やさしい慢性腎臓病の管理 改訂4版 参照※現在は絶版になっています)
腎臓に負担!リン制限のポイント
- たんぱく質をとりすぎない
- 牛乳、乳製品、卵、小魚を控える
- 加工食品(魚練製品、ハム、ソーセージ、インスタント食品、冷凍食品)を控える
- コーラなどのソフトドリンクを控える
腎機能が低下したら水分管理は必要?
特別医師から水分制限がかかっていない場合は、水分の極端な制限や逆に過剰な摂取は有害になります。
腎臓の悪化を防ぐ!運動療法でおすすめは?

糖尿病や肥満を防ぐために適度な運動が必要です。
運動の目安としては週に3~5回程度、時間にして1日30分前後です。
肥満解消には1回15分以上の継続した運動が必要となりますが、1回10分程度の運動を3回に分けて行っても運動の効果は得られます。
腰や膝を悪くしている方は、温水プールでの水中歩行が推奨されます。
おわりに

投薬時に食事に関して聞かれることが本当に多いため、よく聞かれる疑問に答えるつもりで記事を書きました。
栄養士さんに直接指導してもらえればそれが一番だと思いますが、難しい場合はこんな工夫もあるよ、という参考にしてもらえればと思います。
腎臓病の方への贈り物で困っている方はこちら↓

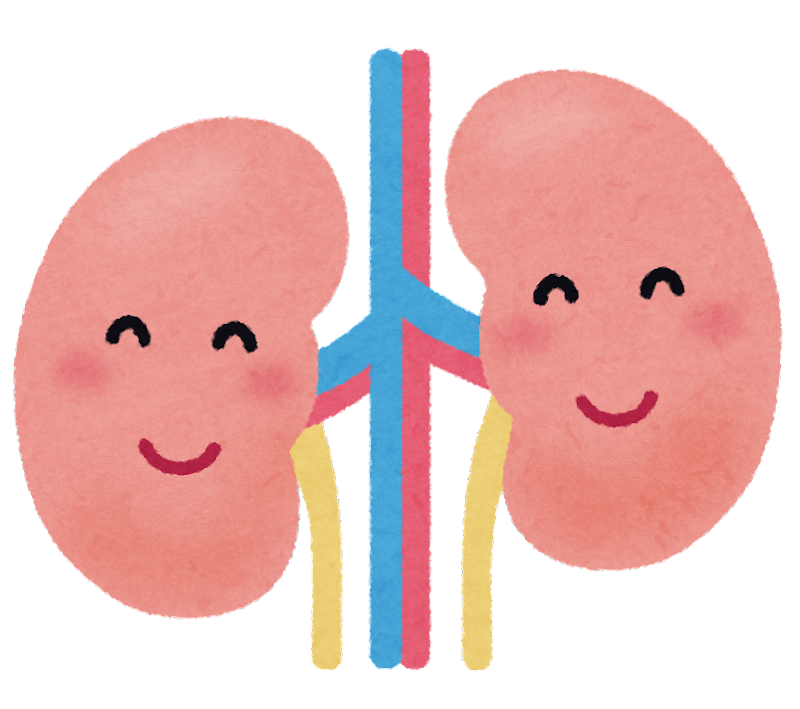
コメント