以前はよく処方されていたベンゾジアゼピン系の眠剤が、専門医以外から安易に処方できにくくなりました。
その代わりに比較的よく処方されるようになってきた「ベルソムラ(スボレキサント)」 「デエビゴ(レンボレキサント)」です。
患者さんからもこの薬に関して聞かれることが多いため、一度よく聞かれる疑問点を中心にまとめてみました。
- ベルソムラ(スボレキサント)の効果、副作用
- デエビゴ(レンボレキサント)とのちがい
- 一般的な眠剤とのちがい
- ベルソムラ(スボレキサント)で悪夢をみるのかどうか
- 薬に頼らない質の高い睡眠をとる工夫
ベルソムラ(スボレキサント)、デエビゴ(レンボレキサント)はどういう作用、特徴の薬?
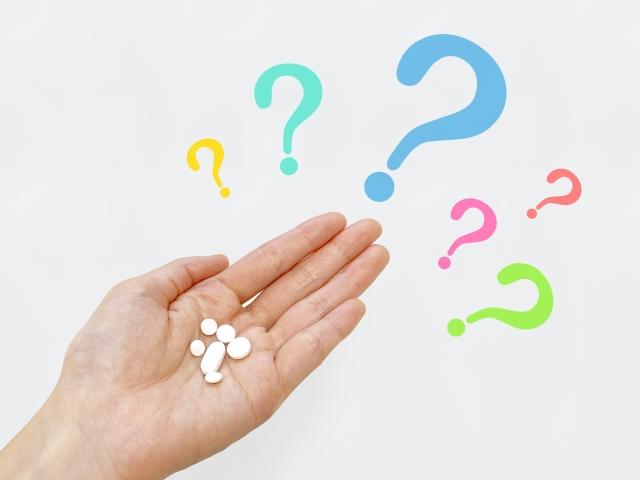
「ベルソムラ」と「デエビゴ」のどちらも オレキシン受容体拮抗薬と言われる薬です。
「ベルソムラ」、「デエビゴ」の作用メカニズムには、”オレキシン“という覚醒に関係する物質が大きく関係しています。
しかしオレキシン神経活動が高く維持されすぎると、覚醒システムが過剰に働き、不眠を引き起こしやすくなると考えられています。
「ベルソムラ(スボレキサント)」、「デエビゴ(レンボレキサント)」 はこのオレキシンの受容体に働き、オレキシンの働きをブロックし、覚醒物質を抑え、睡眠状態にスイッチさせることで睡眠作用をもたらします。
入眠、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害にも有効
「ベルソムラ」「デエビゴ」の最高血中濃度到達時間は約1.5時間、半減期(血中濃度が半分になるまでの時間)は「ベルソムラ」は10時間、「デエビゴ」は50時間とされています。
また半減期は長く、中途覚醒や早朝覚醒、熟眠障害にも有効ですが、明け方になると生理的なオレキシンが上昇して、オレキシン受容体を「ベルソムラ」や「デエビゴ」から奪って、覚醒が優位になって目が覚めます。
総括すると、全体の睡眠を良質なものにして延ばす薬と考えるといいと思います。
ベルソムラ、デエビゴの服用タイミングはいつ頃がいい?
「ベルソムラ」「デエビゴ」は食事の影響で効果(AUC)が1.2倍、2時間効果が出るのが遅れると報告されています。
可能であれば食後3時間くらい経ってから服用した方がいいでしょう。
ベルソムラ、デエビゴはどのような副作用がある?
- 飲みなれない方だと、強い眠気が次の日に残る場合があります。車の運転に注意喚起されているので、服用開始や増量時には注意してください。
- 悪夢【ベルソムラ(4.7%)、デエビゴ(1~3%)】を起こすと言われています。
- 頻度は低いですが、ナルコレプシー(突然眠気に襲われる病気)が悪化する恐れがあります。
なぜベルソムラ(スボレキサント)、デエビゴ(レンボレキサント)では悪夢がおきるの?
しかしこの副作用は、本人のストレスの程度に影響を受けるともいわれています。
 かばこ
かばこ投薬をしていて悪夢が気になっている人に出会ったことはありません。
本人が気にならない程度の軽いものが多いのではないかと思われます。
ベルソムラ(スボレキサント)とデエビゴ(レンボレキサント)のちがいは?


デエビゴはベルソムラよりもあとに開発された薬です。
- ベルソムラ(スボレキサント):2014年発売
- デエビゴ(レンボレキサント):2020年発売
どちらもまだジェネリック医薬品は発売されていません(2024.4現在)
ベルソムラとデエビゴの効果のちがいは?
「デエビゴ」は「ベルソムラ」に比べ、より強くオレキシン2受容体を阻害します。
オレキシン2受容体がより覚醒に関与するとされており、「デエビゴ」は「ベルソムラ」より睡眠に対する作用が強いと考えられています。
ベルソムラは一包化できない!
また、 「デエビゴ」 は「ベルソムラ」の湿気に弱い欠点、相互作用が多い欠点を改善し、「ベルソムラ」に比べて保管がしやすく、他の薬への影響が少ないというメリットもあります。(「デエビコは一包化できます。)
溶出試験において,PTPから取り出した直後のベルソムラ® 錠からのスボレキサントの溶出率は2時間でほぼ100%に達したのに対し,一包化後に30日間室温保存した場合84%,無包装で30日間室温保存した場合78%と有意に減少した.
このことから,ベルソムラ®錠の一包化はスボレキサントの溶出性を少なからず変化させることが明らかとなった.
スボレキサント(ベルソムラ®)錠の一包化調剤における安定性の検討/医療薬学より抜粋
一般的な眠剤(ベンゾジアゼピン系)とベルソムラやデエビゴは何がちがう?


ベンゾジアゼピン系【代表的な薬剤:ハルシオン(トリアゾラム)、レンドルミン(ブロチゾラム)】や非ベンゾジアゼピン系【代表的な薬剤:マイスリー(ゾルピデム)、アモバン(ゾピクロン)】は、GABAに影響を及ぼし、強引に疲労感のような眠気を引き起こします。
また、筋弛緩作用、鎮静作用、認知機能に対する影響も指摘されています。
高齢者への処方は本当に必要かどうかよく確認したほうがよい薬です。
ベルソムラやデエビゴは依存性、耐性はでるの?
本来の眠気を強める形なので、まったく依存性がないわけではありません。
認知機能に対する影響や、筋弛緩作用もほとんどないと言われています。
また睡眠薬を急に減量したり中断した場合に、以前より強い不眠が出現するという反跳性不眠が起こりにくいとされています。
そのため、「安全性の高い眠剤」であると言えると思います。
一般的な眠剤とちがって処方制限がない
主に眠剤と言われるベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系共に30日の処方日数制限があるものがほとんどです(一部ないものもあります)
一般的な眠剤からベルソムラ、デエビゴに切り替える場合の注意点
- ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系の眠剤のどちらからの切り替えの場合でも、効果が弱く感じる可能性があります。
- ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系の眠剤を、高用量を服用している場合は、いきなり切替えると離脱作用が起こる為危険です。医師の指示に従って徐々に切り替えていくようにしましょう。
ベルソムラ、デエビゴは頓服(眠れないときに飲む)で服用していい薬?
基本的には定常状態(連日服用で血中濃度が一定になる)になる薬であり、連日服用2日後に本来の効果が出る薬の為、頓服では効果が立証されていません。(メーカー確認済)
ただ、医師から許可があり、頓服で服用している方もいます。
ベルソムラ(スボレキサント)やデエビゴ(レンボレキサント)との併用に注意が必要な薬は?


ベルソムラは禁忌薬がおおめです。
CYP3Aを強く阻害する薬とは併用禁忌となっています。



CYP3Aとは、肝臓に主に存在(皮膚などほかのところにもいますが…)し、身体に入った薬剤を無効化(代謝)する酵素の事です。
この酵素を阻害されると薬が代謝されず、血中濃度が上がってしまいます。
具体的には…
- イトラコナゾール(商品名:イトリゾール)
- クラリスロマイシン(商品名:クラリシッド)
- リトナビル(商品名:ノービア)
- ネルフィナビル(商品名:ビラセプト)
- ボリコナゾール(商品名:ブイフェンド )
今の薬局に勤め始めてから3回くらい、クラリスロマイシン+ベルソムラのセットをお薬手帳で見かけました。
この場合のクラリスロマイシンは耳鼻科、歯科で出ていることがほとんどで、耳鼻科、歯科ではあまりベルソムラに触れる機会がない為、医師が禁忌であることを知らずに処方しているようです(そして薬局も禁忌に気が付かずに調剤)。
私がお薬手帳で見た際には、クラリスロマイシンの処方日数が短期間の為、飲み終わっていました。
併用禁忌だと知らずに飲んでしまった!どうしたらいいの?
基本的に気が付いた時点で医師に相談した方がいいと思います。
禁忌薬を服用すると、ベルソムラがどの程度血中濃度が上がるかに関してはデータがない為わかりませんが、2倍から3倍程度になるのではないかと考えられます。
もともとベルソムラはそれほど副作用が強い薬ではないため、短期間血中濃度が2倍になってしまったとしても大きな問題ではないと思います。
デエビゴには併用禁忌はないの?
しかしながら「ベルソムラ」と類似の薬が併用注意として報告されているため、デエビゴの効果が強く感じる場合は医師に相談したほうがよいでしょう。
睡眠がよくとれるようになる工夫(生活習慣や食事)


できれば薬に頼らずによい睡眠をとりたいですよね?
そこで、生活のなかでできる工夫をまとめました!
エーザイの患者向け資材 【眠りの為の12ポイント】参考に作成しました。
質の良い睡眠をとれる生活習慣の工夫
- 定時の離床
- 朝方の日光浴
- 午睡の制限
- 就寝前の過剰な水分摂取を控える
- 寝る前のアルコールの制限
- 寝る前のコーヒー、紅茶、緑茶などカフェインの含まれるものの制限
- ニコチンの制限
- 静かな就寝環境
- 寝る前のブルーライト
具体的にひとつずつ解説していきます!
寝る前のアルコール、カフェイン、ブルーライトには控えましょう
薬剤との相互作用のみならず、アルコール自体に睡眠を浅くする作用、利尿作用がある為、夜中に起きやすくなってしまい、睡眠の質を下げてしまいます。
カフェインも同様に利尿作用があるので注意が必要です。
テレビやパソコン作業によるブルーライトの影響で頭が朝だと勘違いしてしまうことがあるため、寝る直前までこれらの作業をすることはお勧めできません。
お風呂も効果的に使いましょう
入浴後にだるいと感じるくらいが程よい加減です。しばらくすると眠気を催します。
就寝1時間前くらいの入浴がおすすめです。
就寝直前に熱い風呂に入ると疲れがとれた感じがしますが、目がさえて眠りにくくなることがあります。
手浴や足浴でも効果があると言われています。
朝日を浴びて生活リズムをリセット
寝室のカーテンを開けて日光を入れたり、ひなたぼっこをするなど、20~30分間朝日を浴びて体を目覚めさせましょう。
日中に適度な運動をして、身体も心もリフレッシュさせましょう
自分のペースで構わないので、体調のいい日は散歩を習慣にしてみましょう。
眠くないときは無理に寝ようとしなくても大丈夫です
眠くないときは無理に布団に入らず、いったん部屋を明るくして本を読んだりして夜を楽しむようにしましょう。
楽しんでいるうちに緊張がとけ、リラックスして眠くなってくるものです。
睡眠時間は8時間必要ない?
年齢に見合った生理的睡眠時間を超えて長く床に就いていると、睡眠の質が全体に浅くなり、夜中に目が覚めてしまう時間が増えてしまうようです。
質の良い睡眠のために食事にもひと工夫を
以下の食品をバランスよくとるのがおすすめです!
- ごま
- 豆類(豆腐、納豆等含む)
- 肉
- 魚
- ナッツ
- 乳製品
まとめ
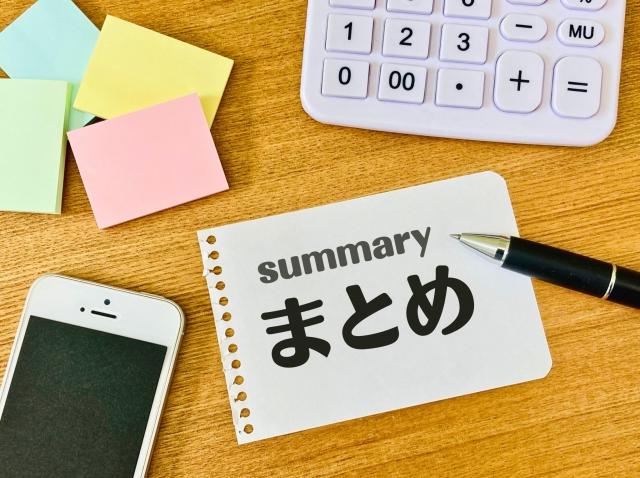
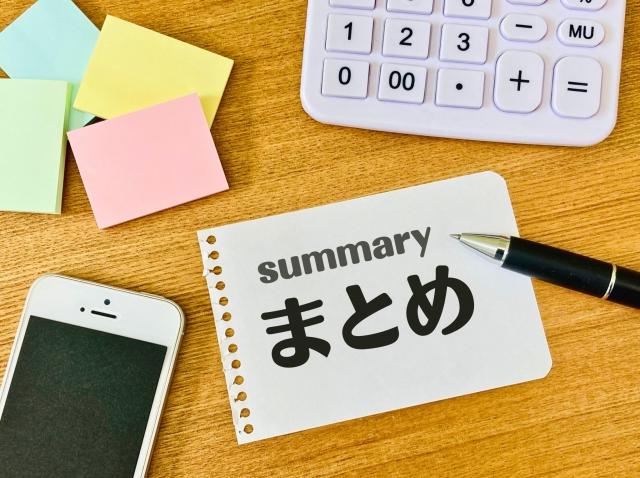
新聞等で「危険な眠剤」と騒がれている一般的な眠剤(ベンゾジアゼピン系という)とは種類が異なります。
依存性や転倒リスクがほとんどない、安全性の高い薬です。
しかし飲み方には少し注意(併用禁忌や食事の影響、連日服用推奨など)をしながら服用を継続していってください。
糖尿病と睡眠の関係に関して知りたい人はこちら↓



コメント