アロプリノール錠は腎機能が低下すると用量調節が必要な薬として有名です。
- アロプリノールとは
- 腎機能が落ちている場合のアロプリノールの副作用とは
- 実際に報告されている副作用例
アロプリノール錠とはどういう薬か
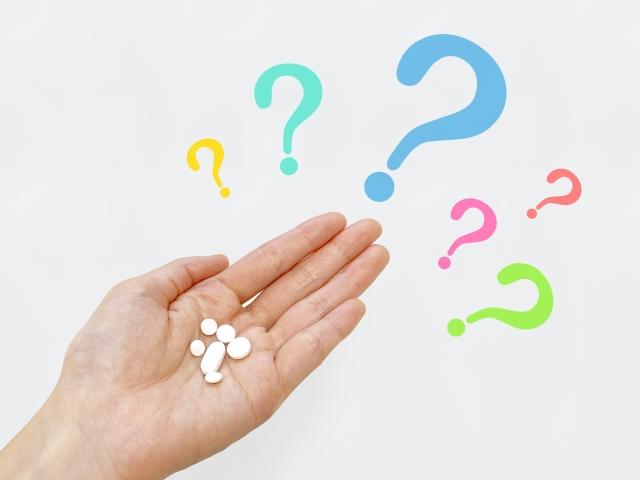
添付文書情報を簡単にまとめました。→添付文書はこちら ザイロリック錠(アロプリノール)
先発品名
先発品名はザイロリック錠で、成分名がアロプリノールとなっています。
効果・効能
尿酸の合成を阻害することで、尿酸値を低下させる作用を持っています。
1日量アロプリノールとして200〜300mgを2〜3回に分けて食後に経口投与するのがスタンダードな使用方法ですが、腎機能に応じた用量調節が推奨されています。
副作用
発疹、消化器症状などが0.1~5%程度、添付文書上は報告されていますが、実際仕事をしていて、消化器症状を訴えた方に遭遇したことはありません。
そのほか、皮疹なども報告されています。
アロプリノール錠は腎機能に応じて、用量調節が必要?下げても効果はでるの?

| 腎機能CCr(ml/min) | アロプリノール投与量 |
| >50 | 100~300㎎/日 |
| 30<CCr≦50 | 100㎎/日 |
| 30≦ | 50㎎/日 |
| HD | HD終了時100㎎ |
| PD | 50㎎/日 |
CCr≦50あたりから、アロプリノールは100㎎にまで用量を落とすことが推奨されています。
なぜ用量調節が必要?アロプリノール錠の腎排泄率はどのくらいか
アロプリノールの尿中排泄率は10.4%程度とインタビューフォームに記載されています。
腎機能が正常な患者 3 名にアロプリノール 600mg/日を経口投与した場合、尿中へは服用した 76%が排出され、排泄物の割合は、アロプリノール 10.4%、オキシプリノール 73.6%であり、それぞれのヌクレオシドとして 12.5%、3.5%であった
ザイロリック錠 インタビューフォームより抜粋
しかしアロプリノールはキサンチンオキシダーゼによりオキシプリノールに代謝され、オキシプリノールもキサンチンオキシダーゼ阻害による尿酸合成阻害作用をもっています。
消失半減期はアロプリノールでは1~3時間と短いですが、オキシプリノールでは12~30時間と長く、透析患者では125時間にも延長します。
 かばこ
かばこアロプリノール自体の尿中排泄率は高くないけど、活性代謝物の尿中排泄率が高いから、腎機能に応じて用量を調節する必要があるんですね!
アロプリノール50㎎で十分な効果がでるか



根拠に関しては、色々探しましたが発見することが出来ませんでした。
【参考資料】
- ザイロリック添付文書
- ザイロリックインタビューフォーム
- 「高尿酸血症・痛風治療ガイドライン ダイジェスト版」
- 「腎不全と薬の使い方 Q&A 第2版」
- 「腎機能別薬剤投与量POCKET BOOK」
アロプリノールはどのような副作用例が報告されているの?


透析患者さんでは、アロプリノールの副作用発現率が高く、重篤な例や死亡例も報告されているため、注意が必要です。
重篤な副作用としては、汎血球減少症、再生不良性貧血、重篤な肝障害、TEN様の皮膚炎などが報告されており、メカニズムとしては、活性代謝物の蓄積による中毒説や、免疫系を介したアレルギー説がいわれています。
2003年3月27日の厚生労働省の安全性情報によると、重篤な副作用に陥った例の多くが1日200㎎を投与されていたそうです。



アロプリノールの用量をまもっていれば起こらなかった副作用という事ですね。
「高尿酸血症・痛風治療ガイドライン ダイジェスト版」にも以下のようにしっかり記載されているため、用量にはよく注意した方がよいでしょう。
腎不全の患者に過量投与すると、オキシプリノールが大量に血中に蓄積して致死的な中毒症候群を起こすことがあり、腎障害の程度に合わせた投与量の調整が推奨されている
「高尿酸血症・痛風治療ガイドライン ダイジェスト版」
代替薬としてどのようなものが考えられているか
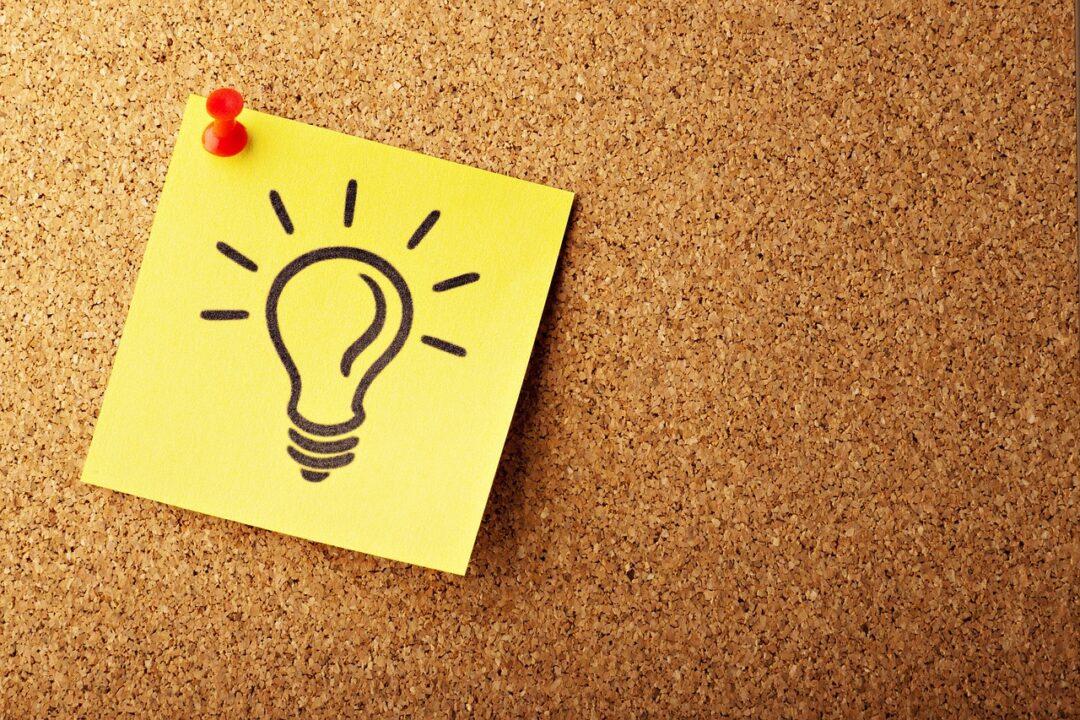
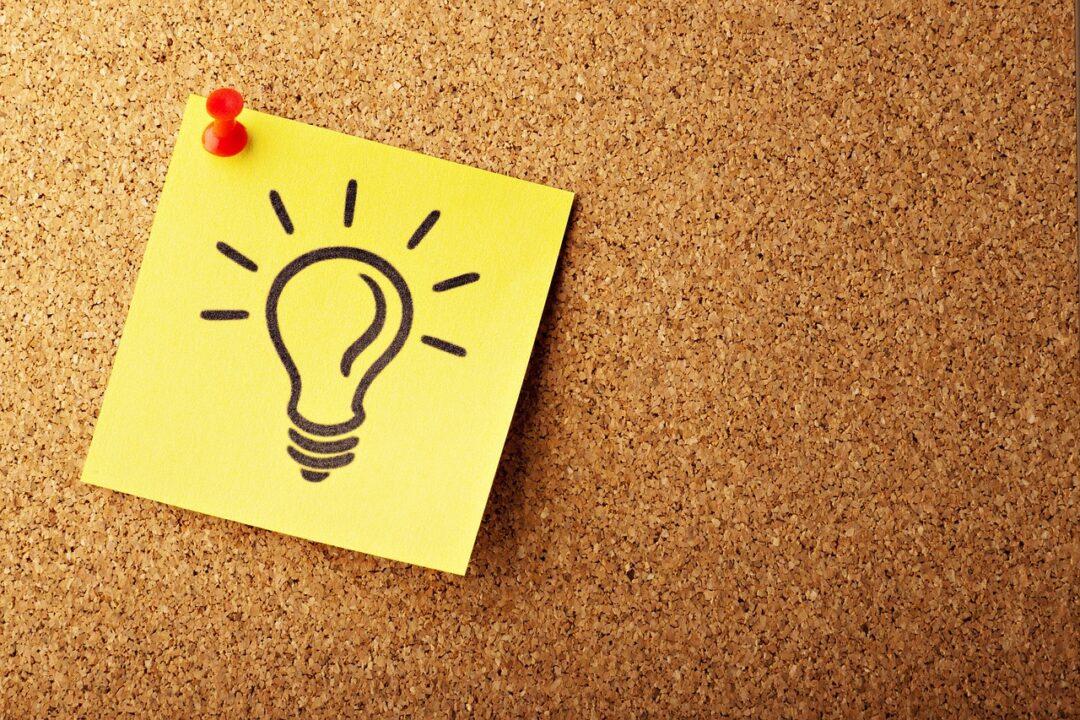
非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤であるフェブリク(フェブキサット)、トピロリック(トピロキソスタット)などが有力候補として「腎不全と薬の使い方 Q&A 第2版」では紹介されていました。
ユリス錠などのURAT1阻害薬に関しては、データが少ないようですが、十分に変更は考えられると思います。
参考にした書籍
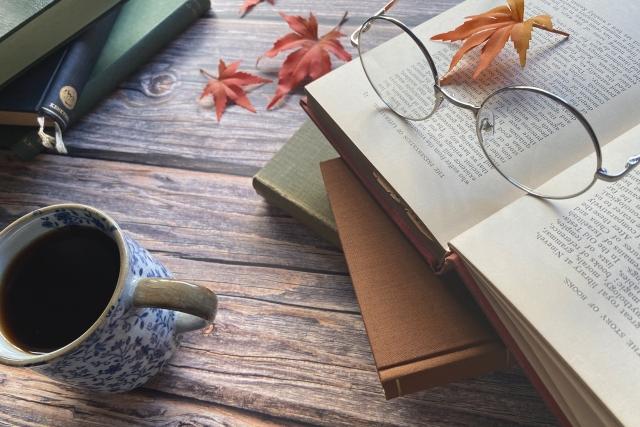
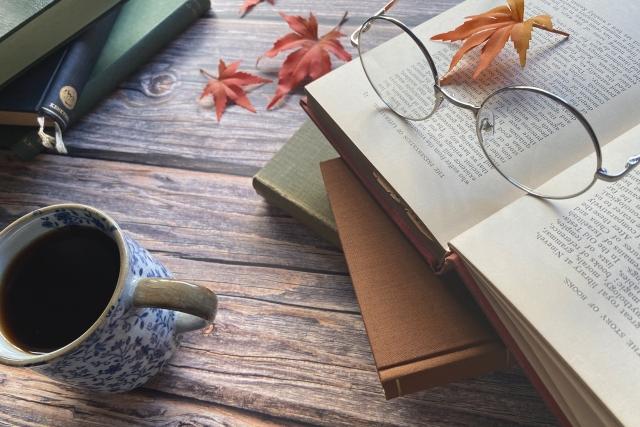
今回の記事作成に使用した書籍を紹介します!
おすすめ度は5段階評価で★~★★★★★までで表現しています。
腎不全と薬の使い方 Q&A 第2版
おすすめ度 ★★★★
私は30%くらいしか理解できず力不足を感じましたが、エビデンスもしっかりしており、腎臓内科や透析施設がある病院で働いている薬剤師は調べるとき用に1冊置いておいてもいい本だと思います。
腎機能別薬剤投与量 POCKET BOOK
おすすめ度 ★★★★★
改訂版が出るたびに買い替えている薬剤師もいます。そして医師が持っているのも何度か見たことがあります。それくらい有名な本です。
まとめ
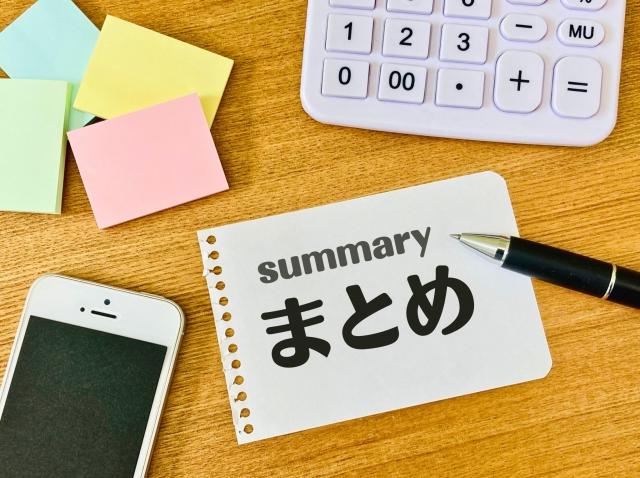
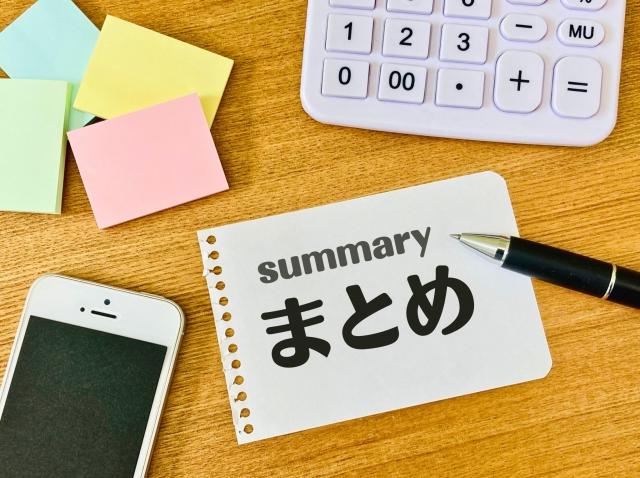
職場で、どんなに腎機能が落ちてもアロプリノール錠を200㎎以上で使い続ける先生がいるため、腎機能に応じた用量調節の必要性に関してまとめてみました。



年配の先生方はアロプリノール錠大好きなんですよね…。

コメント