高カリウム血症治療薬といえば以前はカリメートやアーガメイト(現ポリスチレンスルホン酸Caゼリー)※後発品のみでしたが、気がつけばたくさんの種類の治療薬が販売されています。
現在販売されている高カリウム血症治療薬は、ポリスチレンスルホン酸Ca(先発品:カリメート、後発品:ポリスチレン酸Caゼリー)、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム(先発品:ケイキサレート)、ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム(先発品:ロケルマ懸濁用散)、パチロマーソルビテクスカルシウム(先発品:ビルタサ懸濁用散)です。
この記事では、これらの薬の特徴や違い、新薬のビルタサに関して調べてまとめました。
 かばこ
かばこ私自身もこの記事を書きながら勉強したいと思います!
- 高カリウム血症とは?
- 高カリウム血症治療薬の違いと特徴
- 新薬ビルタサ錠とは?
高カリウム血症とは?基本知識を確認!


高カリウム血症治療薬の説明をする前に、そもそも高カリウム血症って何?という基本的なことをまとめてみました。
高カリウム血症の定義と原因
高カリウム血症とは、血清カリウム濃度が5.5 mEq/L(5.5 mmol/L)を上回る状態を指します。
高カリウム血症は、細胞の代謝や心臓の正常な働きに深刻な影響をもたらす可能性があります。
高カリウム血症になる主な原因としては、腎機能の低下やカリウム排泄を妨げる薬剤の使用、カリウム摂取過剰、細胞破壊を伴う外傷や感染症、さらには代謝性アシドーシスなどが挙げられます。
特に慢性腎不全や糖尿病などの基礎疾患を持つ人は、高カリウム血症の発症リスクが高くなるため注意が必要です。
身体への影響と主な症状
高カリウム血症は、身体にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。
初期症状としては四肢の重さや脱力感、しびれ感、さらには冷感が現れることがあります。
進行するにつれて、呼吸麻痺や胃腸障害、動悸や不整脈といった深刻な症状を引き起こすことがあります。
特に、血清カリウム濃度が7〜8 mEq/Lを超えると心停止のリスクが高まるため、迅速な対応が求められます。



K値が6mEq/Lを超えた場合は、疑義照会をかけるようにしてます。



特に心疾患を持ってる人は不整脈が怖いので、注意してK値をチェックしてます。
治療が必要なケースとは
軽度の場合、症状がないこともありますが、食事療法や原因薬の中止などの対応が必要です。
一方、中等度以上の高カリウム血症では、心電図変化や症状が見られる場合、早急に治療が求められます。
高カリウム血症治療薬としては、ビルタサやロケルマなどの陽イオン交換樹脂製剤が使用されます。
高カリウム血症治療薬を一覧でまとめて解説


高カリウム血症治療薬は、血清カリウム濃度が異常に高い状態を管理し、合併症の発生を予防するために使用されます。
血清カリウム濃度が5.5 mEq/Lを超える場合、特に6mEq/Lを超える場合は処方開始になることが多いです。
それぞれの特徴を見ていきましょう!
高カリウム血症治療薬の薬理作用
高カリウム血症治療薬は、主に腸管内で薬剤成分がもつ陽イオンをカリウムイオンと交換し、吸着したカリウムイオンごと薬剤成分を体外へ排泄させることで結果的に血液中のカリウム値を低下させる薬です。
カリメート、ポリスチレンスルホン酸Ca「三和」、ケイキサレート、ロケルマ懸濁用散、ビルタサ懸濁用散の一覧表
以下に一覧をまとめました。
個人的に他の薬剤よりも優れていると感じたところは淡い黄色で色をつけてみました。ちょっとネックになりそうなところは淡い青色をつけてみました。
| 成分名 | ポリスチレンスルホン酸Ca | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム | パチロマーソルビテクスカルシウム |
| 先発品名 | カリメート | ケイキサレート | ロケルマ懸濁用散 | ビルタサ懸濁用散 |
| 販売日 | 1975年10月 | 2011年2月 | 2020年5月 | 2025年3月※2026年3月まで投与制限アリ |
| 適応 | 急性および慢性腎不全による高カリウム血症 | 急性および慢性腎不全による高カリウム血症 | 高カリウム血症 | 高カリウム血症 |
| 剤型 | 散剤、ドライシロップ、液剤、ゼリー剤 | ドライシロップ、散剤 | 懸濁用散 | 懸濁用散 |
| 後発品の有無 | あり | あり | なし | なし |
| 味 | 散剤は無味無臭。ドライシロップ、経口液は白くドロッとした液体で軽度甘み。ゼリー剤は甘くザラつきあり。 | 散剤は無味無臭。ドライシロップはリンゴ味。 | 無味無臭。ドロっとして苦みがあるとの報告もある。 | 無味無臭。ドロッとして苦みがあるとの報告もある。 |
| 飲みやすさ | △ | △ | 〇 | 不明 |
| フレーバー | 経口液、ゼリーにフレーバーあり | なし | なし | なし |
| 用法用量 | 1日量を2~3回に分ける | 1日量を2~3回に分ける | 開始時1日3回2日間、以降は1日1回 | 1日1回 |
| 交換イオン | Ca | Na | Na | Ca |
| K値以外の電解質に関する注意 | 血清Ca上昇に注意 | 血清Na上昇に注意 | 食塩摂取量に配慮 | 記載なし |
| 腸閉塞患者 | 禁忌 | 記載なし | 記載なし | 禁忌 |
| 貯蔵方法 | 室温保存 | 室温保存 | 室温保存 | 2〜8℃で保存 |
| 副作用(主に便秘と腸閉塞リスクに注目) | 便秘5%以上、腸閉塞リスクあり | 散:1%以上5%未満 ドライシロップ:頻度不明 | 便秘10%未満 | 便秘14.5%、腸閉塞リスクあり |
| 相互作用 | ジギタリス製剤、Al,Ca,Mg含有制酸剤または緩下剤 、甲状腺ホルモン製剤 | ジギタリス製剤、Al,Ca,Mg含有制酸剤または緩下剤 、甲状腺ホルモン製剤 | 抗HIV薬、アゾール系抗真菌薬、チロシンキナーゼ阻害剤、タクロリムス | ニューキノロン系抗生物質、甲状腺ホルモン製剤、メトホルミン |
| 価格(通常の1日量で計算) | 139.5~279円(成人1日量15~30g/日)※カリメート散★ジェネリックあり | 1日量341.4円(成人1日量39.24g)※ケイキサレート散 | 5g1包:1024.3円/包(維持期の成人1日量5g) | 8.4g1包:949.5円/包(成人1日量8.4g) |



味や飲みやすさに関しては、さまざまなブログやSNSの情報も参考にさせていただきました。



カリメート液とポリスチレンスルホン酸Caゼリーにはさまざまなフレーバーがあり、メーカーから薬局を通じて無料で手に入れることができます。



散剤は基本的に懸濁して服用します。
高カリウム血症治療薬に共通する注意事項
高カリウム血症治療薬は、カリウムを低下させる薬です。
血清カリウム値が3.5mEq/L未満に低下した場合、本剤の減量又は中止を考慮すること。血清カリウム値が3.0mEq/L未満に低下した場合、本剤を中止すること。血清カリウム値に応じて、カリウム補充の必要性を検討すること。



薬によるK値の下がりすぎに関してトレーシングレポートを出したことがあります。
トレーシングレポートに関する記事はこちら


本剤の投与では、消化管への蓄積を避けるため、便秘を起こさせないよう注意すること。また、便秘を起こした場合は、浣腸等の適切な方法を用いて排便させること。
ビルタサとロケルマ:それぞれの特徴と違い
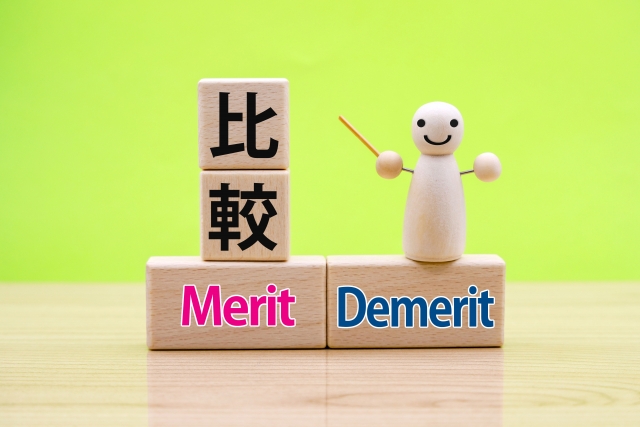
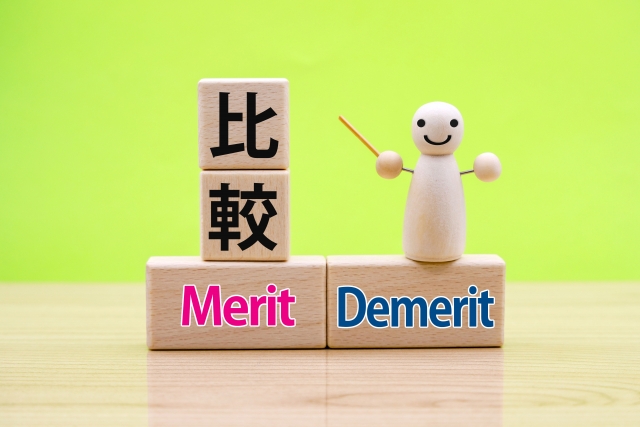
さきほど、ざっくりと高カリウム血症治療薬に関してまとめましたが、ここでは、比較的新しいロケルマとビルタサに絞って詳しく調べて違いをまとめました。
ビルタサの基本情報と効果
ビルタサは、陰イオンポリマー(活性本体のパチロマー)とカルシウム・ソルビトールの対イオンで構成される非吸収性の陽イオン吸着ポリマーで、通常1日1回服用します。
ナトリウムを含まないため、浮腫など体液負荷を高める副作用が理論上想定されていません。
そのため、食塩制限などによる体液管理を含め、疾患管理が推奨されているCKDや心不全を併発する高K血症患者に対して、有用な治療選択肢として期待されています。
しかし、相互作用という点では注意が必要です。



同時服用で、AUCが20%程度低下すると報告されています。
また、ビルタサは効果発現が緩徐です。
ロケルマの基本情報と効果
ロケルマ(ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物)は、比較的新しい薬剤であり、その作用機序がユニークです。
ロケルマは1日1~3回服用されることがあり、急性の高カリウム血症の治療だけでなく、慢性の管理にも用いられます。
効果発現の速さや便秘に関しては、以下の記載がありました。
(HARMONIZE Global試験)の補正期治療において、本剤10gを1日3回投与した
ところ、投与後24時間で対象患者の63.3%、48時間で89.1%が正常血清カリウム
値を示した。ロケルマ インタビューフォームより抜粋
高カリウム血症の患者に本剤を10gを1日3回投与した場合1時間後にはカリウムが低下し始め、24時間後には83.3%がカリウムは基準値内になる。
従来の有機ポリマー樹脂ポリスチレンスルホン酸ナトリウムだと92%膨張するが、本剤は17%縮む。
慢性腎臓病の治療薬の注意点|埼玉メディカル医療センターより抜粋



カリメートなどのイオン交換樹脂は、3日間服用でー1.0mmol/L低下している試験結果があるようです。
作用機序の違いを比較
ビルタサとロケルマの最大の違いは、その作用機序にあります。
ビルタサはカルシウムをベースとした陽イオン交換樹脂で、腸管内でカリウムイオンをカルシウムイオンと交換することによってカリウムを除去します。この仕組みは腸管内のpHの影響を受けにくく、幅広い患者に使用されやすい特徴があります。
一方、ロケルマはジルコニウムを基礎とする非ポリマー無機陽イオン交換剤で、選択的かつ効率的にカリウムを捕捉します。他の電解質への影響が少ないため、電解質異常が懸念される患者においても使用が推奨される場合があります。
保管方法の違い
ロケルマが室温保存であるのに対し、ビルタサは原則冷蔵庫(2~8℃)で保管することとなっています。
使用するタイミングと注意点
ビルタサとロケルマの選択や使用タイミングは、高カリウム血症の重症度や患者の基礎疾患によって異なります。
急性の高カリウム血症で迅速な対応が求められる場合は、ロケルマが優先される傾向があります。
一方、慢性の管理が必要な場合や腸管のpHに影響を受けにくい治療が求められる場合には、ビルタサが適しています。
副作用に関しては、ビルタサはカルシウム濃度の変動に注意し、ロケルマでは消化器症状や他の薬剤との相互作用に注意が必要です。
ビルタサとロケルマの違いを表でまとめました
ビルタサとロケルマは従来の高カリウム血症治療薬よりもK結合能が高いという特徴があります。
その他の特徴に関して、以下の表にまとめました。
メリットとして考えられる箇所は淡い黄色で、デメリットになる可能性があるところは淡い青で色付けしました。
| 薬剤名 | ビルタサ(パチロマーソルビテクスカルシウム) | ロケルマ(ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物) |
| 発売日 | 2025年3月※2026年3月まで投与制限アリ | 2020年5月 |
| 適応 | 高カリウム血症 | 高カリウム血症 |
| 用法用量 | 1日1回 | 開始時1日3回2日間、以降は1日1回 |
| 剤型 | 懸濁用散 | 懸濁用散 |
| 交換イオン | Ca | Na |
| K以外の電解質への影響 | 記載なし | ほぼなし |
| 腸閉塞患者への投与 | 禁忌 | 記載なし |
| 便秘頻度 | 便秘14.5%、腸閉塞リスクあり | 便秘10%未満 |
| 貯蔵方法 | 冷蔵庫(2~8℃) | 室温(1~30℃) |
| 相互作用 | ニューキノロン系抗生物質、甲状腺ホルモン製剤、メトホルミン | 抗HIV薬、アゾール系抗真菌薬、チロシンキナーゼ阻害剤、タクロリムス |
| 効果発現時間 | 遅め(7時間程度で効果発現) | 比較的早い(1時間程度で効果は出始める) |
| 水以外への懸濁 | 緑茶 、麦茶 、ウーロン茶 、紅茶 、コーヒー 、ネクター(アプリコット、桃) ジュース(オレンジ、リンゴ、クランベリー、ブドウ、パイナップル、洋ナシ)、牛乳 、ヨーグルト 、ゼリー 、プリン(バニラ、チョコレート)、アップルソース 、とろみ調整剤 | 記載なし |
| 価格(通常の1日量で計算) | 8.4g1包:949.5円/包(成人1日量8.4g) | 5g1包:1024.3円/包(維持期の成人1日量5g) |



ビルタサは1日1回でよいというシンプルさと、水以外の懸濁のしやすさ、Naを含まず、吸収されないため、浮腫や全身副作用の低さがメリットですね。



一方、冷所保存であることや、便秘や相互作用の多さが気になりました。
2026年3月までは14日処方制限がかかります。今後に期待ですね。
参考資料
- 慢性腎臓病の治療薬の注意点|埼玉メディカル医療センター
- ビルタサ添付文書
- ロケルマ添付文書
- ロケルマインタビューフォーム
- ナトリウムを含まない高カリウム血症薬|日経メディカル
- Randomized Clinical Trial of Sodium Polystyrene Sulfonate for the Treatment of Mild Hyperkalemia in CKD
高カリウム血症治療薬はどれを選べばよい?


処方薬を決めるのは医師ですが、薬剤師として意見を求められることもあります。
そんなときの情報源としてまとめてみました。
患者の状態に応じた治療の選択
例えば、軽度の高カリウム血症では、食事の改善やカリメートやケイキサレートのようなポリスチレンスルホン酸などの治療薬が選択されることがあります。
一方で、中〜重度の高カリウム血症では、ロケルマやビルタサが選択され、より即効性が求められる治療が必要となり、ロケルマなどの高カリウム血症治療薬が使用されることがあります。
高カリウム血症に頻出の副作用である便秘が気になる場合は、比較的便秘になりにくいロケルマやケイキサレートがおすすめです。
併用禁忌と副作用のリスク
腸閉塞がある患者さんには、ビルタサやポリスチレンスルホン酸Caは禁忌となっています。
Naを含むケイキサレートやロケルマは食塩摂取量に注意が必要です。同様に、Caを含むカリメートやビルタサは血清Ca値上昇に注意が必要です。
薬との相互作用という点では、ビルタサは抗菌薬やメトホルミンのAUCを20%下げてしまうため、2時間程度時間を空ける必要があります。
飲みにくさや経済的なものを考慮する
高カリウム血症治療薬は、長期で続ける場合があります。その場合、経済的な負担も考慮する必要があります。
ポリスチレン酸スルホン酸Caのみ後発品が存在するため、比較的価格を抑えることが可能です。
また、飲みにくさを訴える場合は、フレーバーのあるものやドライシロップ、ゼリー剤、ビルタサのように他の食品に混ぜることが可能なものなどを選択肢に入れることも必要です。
生活習慣改善と治療のバランス
高カリウム血症の治療においては、薬剤治療だけでなく、生活習慣の改善も重要な要素です。
カリウムの摂取量をコントロールするためには、食事療法が推奨されます。
カリウムを多く含む食品は以下のようなものがあります。調理方法にも注意してみましょう!
カリウムを多く含む食品の例
- 果物::バナナ、メロン、アボカド、キウイフルーツ、さくらんぼなど。
- 野菜::ほうれん草、春菊、かぼちゃ、さつまいも、里芋、じゃがいも、にんじんなど。
- 豆類::大豆、小豆、納豆、煮豆など。
- いも類::さつまいも、里芋、じゃがいもなど。
- 海藻類::昆布、干しひじき、あおさ、わかめ、焼きのりなど。
- その他::魚類、肉類、木の実類。
カリウムを多く含む食品のポイント
- 加工されると減る:生の食品、特に野菜や果物、海藻類に多く含まれています。
- 調理方法の工夫:カリウム制限が必要な場合は、調理方法を工夫することでカリウムを減らすことができます。
- ジュースも注意:100%の果物ジュースは栄養素が凝縮されているため、カリウムも多く含みます。
まとめ
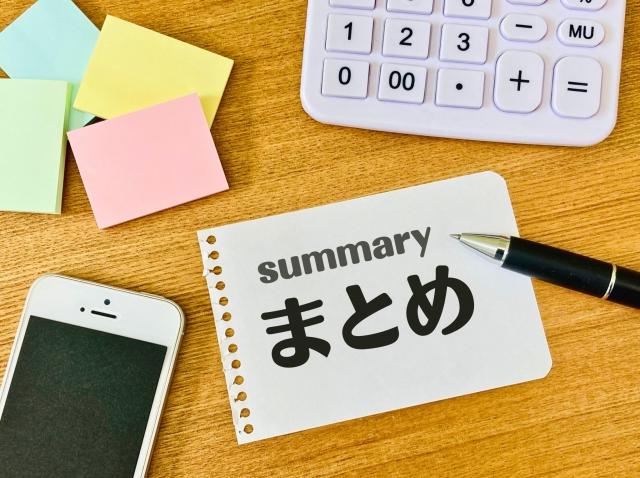
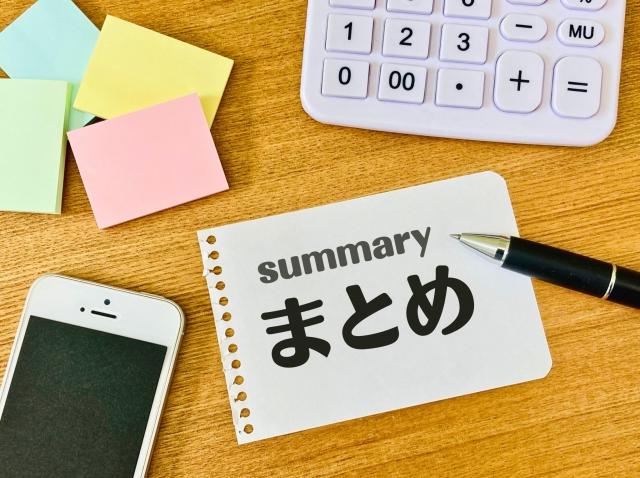
この記事では、高カリウム血症治療薬に関して、「高カリウム血症とは何か」というところから、薬剤のポイントや特徴、最新の治療薬であるロケルマとビルタサに関して深堀して調べました。
簡単に要点をまとめると以下のようになります。
- 高カリウム血症は血清カリウム濃度が5.5 mEq/Lを上回る状態。6mEq/Lを超えたら要注意
- 高カリウム血症治療薬にはNaとCaを交換イオンにしているもの、他の電解質に影響を与えるものがあり、病態によって使い分ける必要がある。
- 高カリウム血症治療薬の主な副作用は便秘だが、薬剤によって頻度に違いがあり、ポリスチレン酸スルホン酸Caとビルタサは比較的頻度が高めである。
- 腸閉塞の場合は禁忌となる薬剤(ビルタサ、ポリスチレン酸スルホン酸Ca)がある。
- ビルタサとロケルマのどちらも従来型よりもK値低下作用が強めだが、ビルタサは冷所保存と薬剤相互作用に注意が必要である。
- ポリスチレン酸スルホン酸Caのみ後発品があるため、価格を抑えたい場合はこちらが優先される。
- ゼリー剤やフレーバー、他の食品に混ぜてよいものなどがあり、飲みにくさを訴える場合は、こちらも考慮する必要がある。
今回は調べてみたら意外と情報量が多く、比較が難しかったです。
参考になれば幸いです。
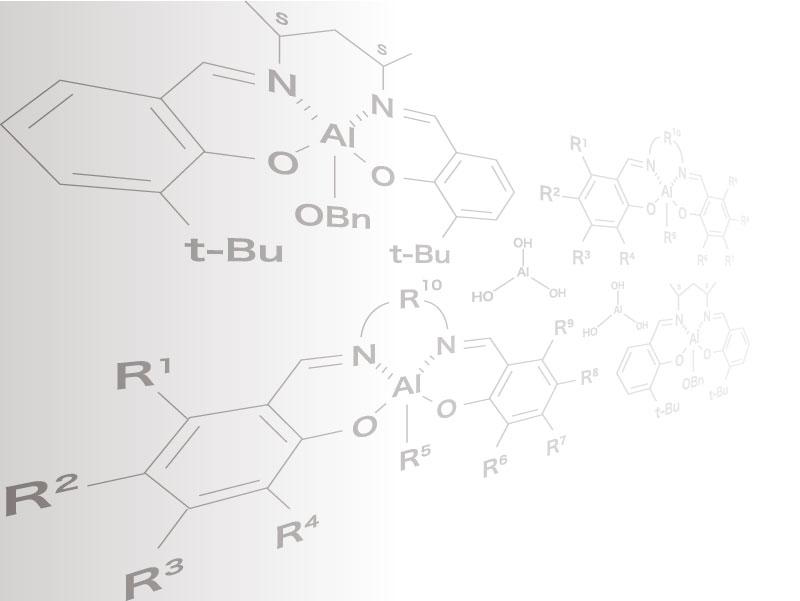
コメント